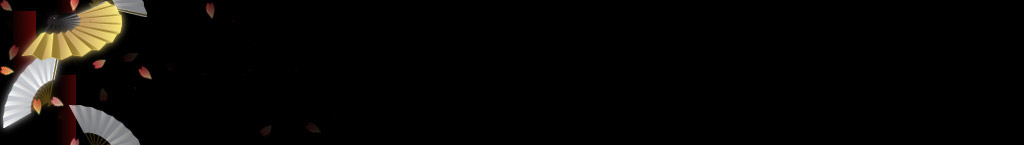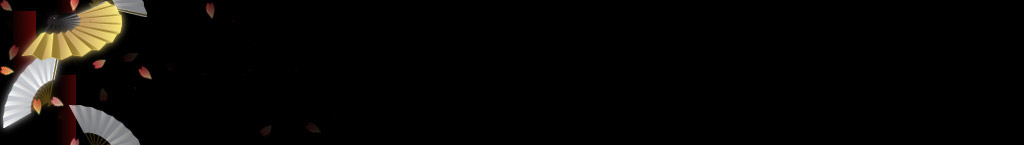
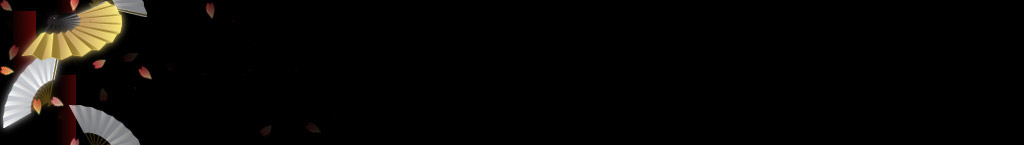
秘すれば…(投稿用)2
二
そして、現在。近江家所有の朱雀能楽堂の稽古場で果月は汗を流していた。
この能楽堂は月華流専用の能舞台があり、素人の教室が開かれている場所である。近江家の演能会の多くはここで開催され、上階は内弟子の住居もあった。
「ありがとうございました」
「はい、お疲れさま」
稽古が終わり、師匠である須藤に礼を済ませると果月は立ち上がって更衣室に向かう。霜月の頃、廊下を歩いていると火照った身体に冷たい風があたって心地良いが、べとつく汗を早く拭いたいと果月は急いだ。戸を開けるとすでに着替えを済ませた二人の若い能役者が雑談をしていた。
部屋にいたのは須藤氏の息子である武と最近通い始めた弟子。二人とも果月と近い歳頃の青年である。
「新年会の演目、何にするんだろ?」
「この次期になんの噂も入ってこないとは珍しいな」
「おう、果月終わったのか」
「ああ……」
「新年会の演目で玄雄先生から何か聞いてないか?」
「いや、何も」
「ふ〜ん。ま、そのうち言ってくるか。あ、果月これ読んだか?」
武が一冊の雑誌を持ち出してきた。
「なんだそれ?」
「日本の伝統芸能を取り扱っている雑誌なんだけどさ、小鳥遊さんのインタビューが載ってるぜ。読むか?」
「ああ、ありがとう」
むふふ、と含み笑いを浮かべる武を不信に思いつつ、差し出された雑誌を受け取る。目次を見ると確かに
対談―――能面師 小鳥遊 友弘
と書いてある。ページ数を確認してそこを広げ、果月はざっと目を通した。最初は普通に能面師としての心構えや素晴らしさ、苦労などを話していたが、息子である果月の話になるとその話一色になる。そこからは果月が読みながら恥ずかしくなってくる内容だった。果月がとても可愛いくて、いい子だと自慢していたからである。武の含み笑いの意味が分かった。
「『可愛い子』ってお前の不頂面にこれ程似合わない言葉はないと思うけどよ」
後ろから武がからかう。
「うるさい」
「お前昔っからファザコンだったんだな。家事をやってるのは知ってたけど、誕生日プレゼント贈ってるのは初耳だったぜ」
「ほっとけ」
果月は三年程前からこの能楽堂に能稽古で通っている。それまで近江家にある稽古場で玄雄に稽古をつけてもらっていたのだが、玄雄が三年前に肺炎で一度倒れ、毎日稽古をみる体力がなくなってしまったのだ。近江家の者に稽古をつけてもらうのが厭だった果月は、一族以外の師範で教室を開いている須藤を紹介してもらった。以来、週の半分はここに通っているのだ。もちろん、果月の能は一流なので他の生徒とは別の個人指導である。ここに通いだしてから、果月は自分の出生を知らない能役者の友人が出来たので楽しかった。特に武は明るくさばけた性格をしているので話しやすい。小さい頃から能の稽古をしているという点で共感できる部分も多く、果月が無口で無愛想でも気にしなかった。果月は武の胸元に雑誌を押し付けて返すと、さっさと着替え始める。
「なあなあ果月、先日入り口で待ってた女の子から手紙もらってただろ?」
「お前なんでそんなの知ってんだ?」
「あれ、どうなった?」
「手紙はその場ですぐに返した」
「え、話も聞かずにか〜」
「ああ」
「もったいねえ〜可愛い子で俺、タイプだったのに〜」
「じゃあ武が付き合えよ」
「嫌味かよ〜」
果月は12歳の時に『経正』で初シテを舞い、注目され始めた。そして18歳の時に『土蜘蛛』で妖怪の役を見事に舞って、皆を驚嘆させた。果月が凛とした美青年という事もあって、しばしばマスコミから取材の依頼がくるようになったが、近江家の者は彼の出生が露見するのを恐れて、一切応じないようにと命令してきた。果月としても騒がれるのは不本意だったので、命じられるまでもなく断り続けている。だが、舞台に立つ以上、目をつける人はいるものだ。成長するにつれ、精悍さを増していく果月に熱をあげる女性ファンが多くなってきていた。ファンレターを送ってくるぐらいならいいが、自宅に訪ねて来たり、この能楽堂で待ち伏せしたりする女性もたまにいて、果月はわずらわしかった。
「この写真の人が果月のお父さんか?」
弟子が雑誌に載っている写真を眺めながら聞いてきた。
「ああ」
「優しそうな人だな。でもあんまり似てないな」
「……母親似なんだ……」
これは本当である。
「じゃあお母さん綺麗な人なんだ。会ってみたいな」
「十年前に亡くなった……」
「……あ…ごめん……」
「別に構わないよ…じゃあ、お先に」
「おう、またな。明日の稽古は近江家か?」
「ああ、もしかしたら、新年会の話がでるかもしれないな」
「なんか分かったら教えてくれよ」
「ああ」
果月が出て行くと
「あ〜もったいねえな〜めっちゃ可愛い子だったのに〜」
と武がまたも呟いた。
「もてるくせに全然誰とも付き合わないのな」
「昔はちょこっと付き合った女の子いたけど、すぐ別れたみたいだぜ」
「へ〜なんで別れたんだろ?」
「無愛想だからかな?二枚目だし、いい奴なんだけど何考えてるか分からんとこあるから。おまけにファザコンだし」
弟子はもう一度雑誌を見た。
「ファザコンね〜やっぱ似てないや。どっちかというと背の高いとことか十郎先生と似てる」
「でも噂では十郎先生と果月、すっごい仲悪いらしいぜ」
「本当に?」
「ただの噂だけどさ。でも普通玄雄先生が駄目なら十郎先生に稽古をつけてもらわないか?叔父と甥だろ。おまけにあの二人、同じ舞台に立った事ないんだってよ」
「一度も?」
「らしいぜ」
「それは変だな〜」
近江家によほど近い関係者でなければ、友弘と果月が義理の親子だと知らない。近江家の内弟子だった須藤は知っていたが、息子にわざわざ言わなかった。
「お前達まだいたのか?もう閉めるぞ」
「は〜い」
須藤が入って来たので二人の会話はそこで終わった。
果月が家に着いた時、友弘はすでに帰宅していた。
「ただいま」
「おかえり」
友弘も帰ったばかりらしく、台所で夕食の支度をしている。
「手伝うよ」
「ありがとう」
果月は友弘の横に立ってじゃがいもを切りはじめた。今日の夕食は肉じゃがにするつもりのようだ。二人並んで共に夕食を作る姿は、どこから見ても仲良し親子だった。
「そうだ、友弘最近雑誌の取材受けたって言ってたよな。今日読んだぜ」
「ほんと、どうだった?」
「なんで俺の話ばっかり喋ってんだ?」
「喋ってたか?」
「ああ、自分のインタビューなんだからもっと自分の話しなよ」
「話してただろ」
「俺の話の方が長い」
「別にいいじゃないか。インタビューしてくれた人も喜んでたぞ」
「読んでて恥ずかしくなっちまったよ」
「なぜ?」
「…可愛いとか言うから…」
「へえ、そう?」
友弘はくすりと微笑んだ。
「これからはあんまり喋るなよ」
「駄目なのか?」
「駄目」
「自慢の息子なんだから、喋りたくなっちゃうんだよ」
――自慢の息子――
友弘は楽しそうに話したが、果月は胸に焦げ付くような痛みを感じた。彼にとって自分は息子以外の何者でもないのだと思い知る瞬間だからである。他の誰でもない彼に言われた時だけ思い知るのだ。果月にとって友弘はもう義父ではなかった。六年前のあの日から、一人の愛する人になっていたのである。
果月とて、自分のこの気持ちを認めるにはかなりの時間を要した。初めはただ守りたいと思っていた。彼を守る為に強い大人に早くなりたかった。そして彼を傷つける人は許さない、と近付く人々を牽制した。しかし、ある日それは独占欲だと気付いてしまったのだ。自分が友弘を十郎のように凌辱する夢を見たからである。果月は自分の裡に潜む友弘への激情に気付いて驚愕した。
きっと勘違いなのだ、あの出来事を目撃してしまったので、そのせいだと自分に言い聞かせ、忘れようと何人かの女性と付き合ったりもした。結局それは友弘への想いを再認識させただけだった。
自覚してから友弘と普通に暮すのはかなりの忍耐を用した。何しろ相手は義理の父。自分に向けられる好意には鈍感なお人好しで、繊細な人。果月が自分に対して欲望を抱いているなど思いもしないだろう。しかも、十郎に凌辱された過去を持っている…
十郎は六年前に千賀子という大鼓方の名門のお嬢様と婚約し、その一年後に結婚した。結婚式は盛大に開かれたが、友弘と果月は欠席した。親類らはめでたい席に不吉な子が来なくてほっとしたらしく、なんの嫌味も言ってこなかった。おそらく、身の程をわきまえて辞退したと思っているだろうが、果月は友弘が欠席をした本当の理由を知っている。十郎に会いたくなかったからだと。
あの事件の後、友弘は何も変わっていない風を装っていたが、近江の屋敷には滅多に出掛けなくなった。玄雄が肺炎で倒れた時も病院の見舞いだけに留めたのである。こんなささいな友弘の変化に気付く者はいなかった。彼の心の傷の深さを果月は誰よりも分かっているつもりだった。それなのに、自分が十郎と同じ目で友弘を見つめているなんて…
絶対に知られる訳にはいかない。友弘の気持ちを、信頼を裏切りたくないのだ。果月は自分の想いを必死に押さえ付けた。彼の望むいい息子でいよう、その枠の中から決して出まい、と努めてきた。しかし、今のように友弘の無邪気な信頼に触れたり、無防備な姿を自分にさらけだしている時は苦しかった。
いつだったか、能面の作業場で友弘がうたた寝をしているのを見て、愛しい気持ちが溢れて我慢できなくなった時がある。気付いた時には、友弘の唇に触れるだけの口付けをしていた。だがその直後、果月は後悔に襲われた。口付けてしまった事への自責の念ではなく、その行為によって欲望の渦が激しく沸き上がったからである。
柔らかな唇の感触、かすめる吐息が頬をくすぐる。唇を辿って彼の頬に触れると、艶やかな皮膚があの日見た彼の腿の白さを思い出させるのだ。
『駄目だ……』
必死に自分を押さえようとするが、目の前に横たわる彼を思うまま蹂躙したいという欲望は膨らんでいく。
このままあなたを力づくで犯したら…あなたは一体どんな瞳で俺を見るんだろう…甘い声をあげるんだろうか?あの時と同じように…
果月の理性がはじけようとした時、電話の音が鳴り響き、果月は思い留まったのである。
『あの時は心臓が口から飛び出るかと思った…』
「切ったじゃがいもこの鍋に入れてくれるか、果月?」
「え、あ、ああ…」
果月は友弘の言葉で我に返った。思い出していた内容だけに、落ち着かない気分になってしまう。
「きょ、今日帰ってくるの遅かったのか?」
「早川さんの墓参りに行っていたから…」
「…今日…月命日だったか…」
「ああ……」
「そうか…忘れてたな…ごめん…」
「別に果月が謝らなくていいよ」
早川とは友弘の師匠である能面師だが、小夜子と友弘が結婚する前に亡くなった。今二人が住んでいる家は元は早川の物で、遺言により友弘の所有となったのである。友弘は孤児で、小さい頃から手先が器用なのを見込んだ早川氏が、まだ幼い友弘を預かっていた親戚方から引き取ったのだ。その時友弘は8歳、早川はすでに60歳を超えた老人だった。
早川は優しく、修行も丁寧に指導してくれたが、家族として自分を愛さなかったと、友弘は気付いていた。自分は最後まで弟子以上の存在にはなれなかった。
友弘は家族と呼べる人が存在しないのがいつも淋しかった。小夜子が自分との結婚を決意したのは、自らの死期を悟っていたからである。果月をあの近江家に置いたまま死んでしまう訳にはいかなかった。つまり、果月をちゃんと育ててくれる男なら誰でも良かったとも言える。
『ごめんね、ごめんね友ちゃん…』
いつも小夜子は謝ってばかりいた。友弘は謝ってなど欲しくなかった。小夜子が誰でも良かったとしても、彼女の力になれるのなら良かったのだ。昔から憧れていた彼女が自分の家族になってくれたのだから…
昔、早川に「お前の打つ女面は小夜子さんの面影がでるから気をつけろ」と言われた。
『能』は奈良時代に中国から伝来した『散楽』『猿楽』を源とした芸術である。神社などで「五穀豊穣」や「寿命長延」の祝に奉納される舞として発展したが、当時の能面は『翁面』の種類しかなかった。
十四世紀後半に観阿弥、世阿弥の天才能楽師親子によって『能』の一大飛躍がとげられ、新作があいついだ。それに伴い演目に相応しい能面が次々と創造されていったのである。まず、自然力の溢れた鬼神面、ついで神の化身とされる尉面。そこから人間味の溢れる老人、幽玄味の強い男面、女面と誕生していった。江戸時代から今日までの能面は模写の時代で、過去の先人達によって完成されたそれらの面を見て、能面師は「写す」のである。いかにして本面に近い面を打てるかが研究されるようになった。完成された美しい面を「写す」為には無心に打たなくてはならないが、未熟な腕の能面師はどうしても自分の色やくせが滲みでてしまう。友弘も女面を打つ時、自分が美しく愛しいと思っているものを写してしまったのだ。それが小夜子だった。もしかしたら、自分は小夜子に「母」を重ねていたのかもしれない、と友弘は思う時があった。まったく知らない「母」の姿を。しかし、彼女も逝ってしまった…
友弘は一人取り残された空虚な気持ちを今も覚えている。哀しくて、孤独で、一人でぽつんと暗闇の中に立っているような気分だった。葬式が終わった日の夜も、孤独を抱えたまま布団の上に座り込んでいた。すると、襖の外に気配を感じ、開けてみると果月が立っていたのだ。自分と同じく孤独を感じていたのだと分かり、いっしょに布団に入って目を閉じた。果月を抱き締めながら友弘は、心が暖かい想いに包まれていくのを感じた。
『私は…この子を愛せる…』
自分には誰もいない、父母もいない、愛した人も逝ってしまった、けれどこの子がいる。小夜子が残してくれた、たった一人の自分の家族なのだ。腕の中の小さな男の子がとても愛しかった。
彼が甘えられるような存在になろう。喜びも哀しみも分け合っていける、そんな家族になりたい。父親でなくてもいい、大切な家族になれたら…
そう思って以来、彼の為にしっかりした大人にならなくては、と頑張っているのだが。
「友弘、炊飯器のスイッチ入ってないけど、飯あんの?」
「あ!スイッチ入れるの忘れてた」
「まったく…早炊きにするぞ」
「ごめん、ごめん」
『父親がおっとりしていると息子がしっかりするって本当だな』
いつの頃から果月はぼんやりした自分と違ってしっかり者になったな、と友弘は優しい気持ちで笑みがこぼれる。
「そうだ明日の能稽古は近江家かい?」
「ああ」
「…明日、近江の家に注文があった面を届けに行くから、もしかしたら会うかもしれない」
「近江の屋敷に来るのか?」
「…そうだよ…」
近江家には十郎がいる…
友弘が十郎と会ってしまうかもしれない、と果月は不安になる。
「俺が持って行こうか?どうせ行くんだし」
「そんな失礼な真似できないよ。前にも言ったろ」
近江の屋敷には行かないようにしているが、面を納める時は別である。果月に持っていかせるようでは能面師として失格だ。友弘は何よりも自分の仕事に誇りを持っていた。
「十郎が出掛けている午前中に来た方がいいんじゃないか。彼が帰ってくると家の人が忙しくなるから、その前に来た方がいいだろ?」
果月は十郎が出掛けるのを思い出し、さりげなく友弘を促した。
「そうか、じゃあそうするよ」
心無しか友弘はほっとした様子だった。果月もこれで十郎と会わずに済むだろうと安堵した。
果月のこういった言動は、近江家に疎まれている自分のせいで、嫌味を言われるのを避けさせようとしているのだろうと、友弘は思った。
『優しい子だな……』
少しぶっきらぼうだけど、思いやりのある子に育ってくれた。友弘は自分と果月の間に絆があると信じ、幸せだった。二人の互いを大切に想う気持ちは同じだったが、六年前のあの時から狂いはじめている事に、友弘はまだ気付いていなかった。
*
次の日、果月が稽古に近江家を訪れると、十郎はすでにいなかった。彼が戻る前に友弘が来てくれるように祈って稽古を始める。
「違う、もっと間をとって」
師匠である玄雄の檄が飛ぶ。果月が舞っているのは『羽衣』である。彼は三番目の鬘物が少々苦手である為、最近はその演目に重点を置いて練習しているのだ。
『能』の正式な番組は、狂言を挟んで五種類の演目が上演される『五番立て』なのだが、今ではほとんど省略化している。上演される演目の種類は順番が決まっていて、初番目は「神の能」。男神、女神、荒神などが主人公。二番目は「修羅物」といわれる修羅道の地獄に苦しむ武人の曲。そして三番目は「鬘物」という女性を主人公にした幽玄美溢れる曲柄。四番目は「狂乱」別名「雑能物」といい最も人間的なジャンルで、他のどこにも属さない演目がここに入る。現行曲の1/3がこれである。五番目が「切能」。鬼や天狗、竜神などが主人公の強烈なパワーの能で終演するのである。
果月が得意とするのは二番目の「修羅物」や四番、五番の中のダイナミックな舞だ。能役者にしては背も高い方なので、へたすれば舞が大振りに見えてしまう為、優美さを身につけるにはまだまだ修行が必要であった。そうはいっても同じ年頃の能役者の中では郡を抜いている。
小夜子が友弘と結婚した時、能面師の家の子供になるのだから、能楽師の席から排すべきでは、という意見が分家筋の者から出たが、玄雄が頑に拒んだ。
「果月には才能がある。私は自分の孫だから贔屓目で言っているのではない。世阿弥の『継ぐをもって家とす』という言葉が示すように、才能に血は関係ないのだ。本人の気力と才能をつまらぬ確執から潰すのは間違っている」
と言って血筋にこだわる分家の者を黙らせたのだ。舞う事が好きだった果月は祖父にとても感謝している。玄雄の言葉通り、家を出てから心の呪縛がなくなったせいか、果月はめきめきと才能を発揮し始め、今では果月を能楽師にするなという者は一人もいない。
「駄目だ!」
玄雄が果月の背中を突いたので、舞台から落ちてしまう。慣れっこな果月はすぐに起き上がり舞台に戻って稽古を続けるが、見慣れていない弟子達は玄雄の厳しさに驚いていた。
「旦那様、失礼いたします」
女中が稽古場の入り口から玄雄に声をかける。
「お稽古中申し訳ありませんが、小鳥遊様が面を届けに来られました」
「そうか、すぐ行くから部屋で待ってもらってくれ」
「かしこまりました」
「友弘が来てくれたようだ。ちょっと行ってくるから、お前は先程の箇所を繰り返し練習しておけ」
「分かりました」
稽古場を出て行く玄雄を見ながら、十郎が戻る前に友弘が来れたのに、果月はほっと息をついた。
玄雄に面を納め終えた友弘は、女中に見送られて玄関を出た。そのまま門に向って歩いていると、帰ってきた十郎が門をくぐってきたので友弘は息をのんだ。
十郎はグレーの背広姿で、着物を着ている時よりシャープな雰囲気だった。彼自身も驚いている様子で、友弘を見つめてじっと立ちつくしている。二人はしばらく無言で見つめ合っていた。我にかえった友弘は礼をしてすばやく彼の横を通り抜けようとしたが、呼び止められた。
「友弘……」
「…な…んだ…?」
「…俺が…憎いか……?」
一瞬友弘は言葉に詰まったが、静かに頭を横に振った。
「…なぜだ…俺はお前に…」
「……………」
二人の間に沈黙が降りる。
「…十郎…俺は小さい時からお前と友達なのが自慢だった…」
「……………」
「自分の意志をしっかりもってて、名家の出なのに変に驕ったところがなくて、人には見せないけど何十倍も努力家で…」
「……………」
「人を思いやる心ももってる…お前は大切な友人だと思ってた…今でもそうだ…」
十郎ははっきりした物言いをするので誤解されやすいが、つきあってみると間違った事を言っていないと分かるのだ。人に厳しいところもあるが、十郎が誰より厳しいのは自分だった。近江家の跡取りとしての責任と期待を一身に受け、それに応える為に絶えず努力していたのを知っている。そして自分にはとても優しかった…
小夜子との結婚が決まった時、十郎は反対した。
彼女はお前を利用しようとしているだけだ、犠牲になる事はない、もっと自分を大事にしろ。そう言って…
だが、自分は彼の忠告を聞かず小夜子と結婚したのである。反対した彼の言葉の裏にどんな気持ちが潜んでいるのか考えもしなかった。どんな気持ちで自分達の結婚を見ていたのかと思うと胸が痛かった。友弘が十郎を避けるようになったのは、十郎が憎いからではなく、彼をこれ以上煩わせたくなかったからだ。自分の姿を見る度にきっと彼は辛い思いをするだろう、あの時の行動を彼は後悔していると友弘は知っていた。
「……友弘……」
「ん………?」
「…俺は…まだお前を…」
十郎の熱い視線を受けて友弘はとまどう。立ち去ろう歩きだした時、十郎が腕を掴んで引いた。
『え………?』
気付くと背中から十郎に強く抱き締められていた。
「……あ……」
「……友弘……」
肩に感じる十郎の囁きがあの日の熱さと重なる。恥ずかしくてたまらなくなった友弘は、思いきり十郎を突き飛ばして彼の腕から逃げ出した。友弘の後ろ姿を見送り、十郎は自分の手をじっと見つめた。先程まで彼の体温を感じていた手を…
突然、殺気を感じて十郎が視線を巡らすと、中庭から自分を睨み付けている果月が目に入った。彼の瞳は怒りに燃えていて、両の拳を固く握りしめている。十郎は果月とは正反対に涼し気に視線を受け止めていた。やがて十郎が踵を返し、屋敷の中に入っていくと、一人残された果月は止めていた息を大きく吐き出した。丁度、昼休憩に入ったので、友弘はまだいるのかを確かめようと玄関に靴を見に来たのだ。縁側を歩いている時、十郎が友弘を抱き締めている光景が目に入ってきたので、思わず中庭に飛び出した。
全身の血が沸騰するかと思った。まだ身体は熱く、怒りはそう簡単に鎮まらない。すぐに友弘が十郎の腕から離れたが、そうでなかったら自分はどうしていただろう?十郎を殴りつけていたかもしれない。
『あいつはまだ友弘に何かする気か…?』
再び湧いてきた怒りで身体が熱くなる。もう二度と彼を泣かせるような真似はさせない。俺が守ってみせるのだと、あの日誓ったのだから…
「絶対にだ……」
知らずに言葉が果月の口をついて出ていた。寒空の下でしばらく佇み、なんとか落ち着きを取り戻してから稽古場に戻る。
「果月、探したぞ。どこに行っていた?」
戻るなり探していたらしい玄雄に聞かれるが、答えられなかった。
「…すみません…」
「まあいい、話があるので部屋に来てくれ」
家に上がろうとして、果月は自分が足袋のまま中庭に飛び出したのに初めて気がついた。裏は泥がついていて、まるで今の自分の心についた染みのようだと思う。
『…くそ……』
忌々し気に足袋を脱ぎ捨て、裸足のままドカドカと廊下を歩いた。玄雄の和室に入った二人は向い合せに腰を降ろす。
「来年の新年会の演目だが」
「はい」
「お前には『二人静』のツレを演ってもらう」※ツレ…助演の事
「では、シテは?」※シテ…主役の事
「…十郎だ…」
「あいつが!?」
先程の怒りも手伝い、果月が吐き捨てるような口調だったので玄雄はため息をつく。
「あいつとなんて冗談じゃありません。お断りします」
「…お前達の仲の悪さ…なんとかならんのか?」
「……………」
「お前がこの家にいた時からろくに口も聞かなかったし、一度も同じ舞台に立っていないではないか。仮にも叔父と甥なんだぞ。少しでも歩み寄ろうとは思わんのか?」
俺じゃない、あいつが悪いんだ、と果月は心の中で叫んだ。
「十郎は承知したぞ……」
それでも説得するのに時間がかかり、新年会の演目を決めるのが遅れた原因でもあった。
「この世界でやっていく以上、十郎は避けて通れんぞ。近江家の跡取りであり、これから月華流を担っていく人物だ。親である私が言うのもなんだが十郎は素晴らしい能楽師だ。あやつの『井筒』(いづつ)などは、私でさえも感嘆するほどだ」
『井筒』は初恋の幼馴染みと結ばれ、死してもなお慕い続ける女の純愛の舞である。諸国を旅する僧が在原寺に立ち寄った際、「井筒の女と呼ばれる有常の娘」と名乗る里女が現れる。女は井戸の水を汲み上げて、在原業平とその妻の話をして姿を消した。僧が仮寝をしていると夢の中に先程の井筒の女の霊が現れ、業平の形見の衣装を身につけ、恋い慕う舞を舞って消えていくというあらすじである。起伏のない物語で、謡も舞も静かな「静寂の能」であるが、だからこそ純粋な恋の激しさを感じる演目なのだ。作者の世阿弥も「井筒上花なり」という言葉を残している。
三年前の秋の宴能会で十郎はこの『井筒』を舞い、大絶賛された。井筒の女が井戸を覗き込み、水面に映る自分の姿に、恋しい業平の面影を見る名場面では、気品と純粋な恋心に圧倒され、場内は水を打ったような静けさであった。おおげさな雑誌記者などは『世阿弥の再来か!?』とまで評した。あまりに素晴らしすぎて、以後、同流で『井筒』を舞ったのは十郎だけである。
「果月…お前…十郎と舞って比べられるのが怖いのか?」
「な……!違います!」
「では、受けるな?」
「……………」
「これは頼んでいるのではない、命令だ。嫌なら新年会には出さん。どうする?」
「……分かりました……」
果月はしぶしぶ承知した。
「では、本番の時はこの面をつけるがいい」
玄雄が傍らに置いてあった木の箱を果月の前に差し出し、蓋を開ける。中には清々しい『小面』の面が入っていた。『小面』は女面の中でも一番若い十五、六の乙女の面である。
「友弘に依頼してあった面だ。さっき届けてくれた」
「友弘の打った面ですか?」
果月の胸が少し跳ねる。今まで彼の打った面をつけた事はなかったからである。彼はいつも言っていた。
――『能面』は能楽師がつけてこそ完成される。魂を込めるのは能面師だが、命を吹き込みのはお前達能楽師なのだ――と。
友弘の打った面に自分が命を吹き込む任を受けたと分かって、果月は微かな恍惚を覚える。
「彼の打つ『小面』は品があって清楚だ。女面では日本で五指に入る能面師だな」
「はい」
「なにより彼の面は縁起がいい」
「というと?」
「実は十郎が三年前に『井筒』を舞って絶賛された時も彼の面をつけていたのだ」
「え………?」
「それからだ、あいつの『井筒』が見違えるようになったのは…」
果月は心の染みが広がっていく気がして眉をよせた。
「友弘の面は能楽師の感性を磨かせる力があるのかもしれん。もっとも、それを表現できる力量がなければ意味がないが。果月、『二人静』はツレの担う役割が大きい。本来ならばシテと拮抗する役者が舞う役だ。十郎と相舞するとなると生半可な出来では通用しないから心して取り組め」
「……はい……」
宴能会、友弘の打った面、鬘物の演目、三年前の十郎の時と同じ条件が揃っている訳である。
『負けるものか…!』
果月の瞳に炎が灯り始めた。
その後の稽古は『二人静』となり、果月と玄雄の熱の入った取り組み様に誰も声をかけられなかった。玄雄がいなくなった後も果月は時間の許す限り稽古を続け、近江家を出たのは、夕食の時間もかなり過ぎた頃であった。
『友弘心配しているだろうか?』
少し急ぎ足で帰路を歩いていると、友弘の呼ぶ声が聞こえた。
「今帰りか?遅かったな」
友弘が近付いて果月の横に並ぶ。
「ちょっとな。友弘こそどうしたんだ?こんな時間に」
「醤油がきれてたから買いに出掛けたんだ」
友弘が持っていたスーパーの袋を上げてみせたので、果月の気が抜ける。
「どうした?」
「一気に現実的生活感が蘇ってきた…」
「ふふ…お前は今まで幽玄の世界にいたからな」
「まあね……」
二人は並んで歩き始める。ふと見ると友弘の格好は軽装で寒そうだった。
「寒くないのか?」
「ちょっと買いに出ただけだから」
果月は自分がかけていたマフラーをはずし、友弘の首に巻き付けた。
「つけてろ」
「あ、でも果月が寒いだろ?」
「友弘の恰好見ている方が寒い」
「…ありがとう…そうだ、お義父さんに聞いたけど今日持っていった面、お前がつけるんだって?」
「ああ………」
「そうか、嬉しいよ…何を舞うんだ?」
「『二人静』のツレ」
「じゃあシテはお義父さん?」
「……十郎……」
「…そうか…十郎か…お前、彼と同じ舞台に立つのは初めてじゃないのか?」
「そうだな……」
「……果月……」
「なに?」
「……十郎は優しい人だぞ……」
「……はあ……?」
あまりに意外な言葉だったので、果月はすっとぼけた声をだしてしまう。
「……お前や小夜子さんに対する態度は確かに冷たかったと思う。でも、中傷したり、嫌味を言ったりはしていないだろう?何も言わないのも優しさだと思うぞ」
「……………」
果月の怪訝そうな視線に気がついた友弘は、さらに言葉をつないだ。
「お前だって相手が傷つくかもしれないから、言いたくても我慢する時があるだろう?」
「え………」
自分の心を見透かされた気がしてドキリとする。
「十郎は家の跡取りとしての責任を真っ当する為、たくさん我慢しているんだと思う…分かりにくいだろうけど、ちゃんと人の気持ちを考えてるし、身勝手な人じゃないよ」
今日、友弘は面を納めに行った時、玄雄と少し話したのだが、彼も十郎と果月の仲違いに胸を痛めていた。同じ能役者として少しでも歩みよってくれたら、とぼやいていたのである。今度の『二人静』は二人の仲が少しでも良くなるように、玄雄がセッティングした気がする。
「お前と十郎が仲良くなってくれたら、お義父さんも喜ぶし俺も嬉しいよ」
「……………」
黙って友弘の言葉を聞いていた果月は、ここが外で良かったと思った。もし、二人きりの室内だったら自分が何をするか予想できないからだ。隣で自分を信頼して歩く友弘をひどく裏切ってやりたい気分だった。
果月は友弘より頭一つ分ぐらい背が高く、体格も勝っている。『能』は静かな動きの印象があるが、実は体力勝負の芸能で、かなりの持久力が要求される。涼し気な着物の下はいつも汗まみれで、3歳の時から稽古をしている果月の身体は、しなやかで無駄のない筋肉がついていた。力も完全に自分の方が強く、決して適わないと友弘に思い知らせてやりたかった。押さえ付け、ねじ伏せて、もう二度とそんな事を言うなと命令するのだ。十郎と仲良くしろなどと…!
凶暴な支配欲を押さえる為、果月は気付かれないよう何度も深呼吸せねばならなかった。少しでも家に着くのを遅らせる為わざとゆっくり歩く。まるで重い荷でも背負っているような気がして、六年前にも同じ事を感じたのを思い出す。ただし『重荷』を背負っているのは今度は自分の方だった。にがく、苦しい恋の重荷を…