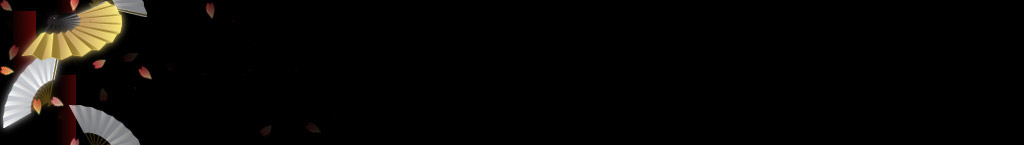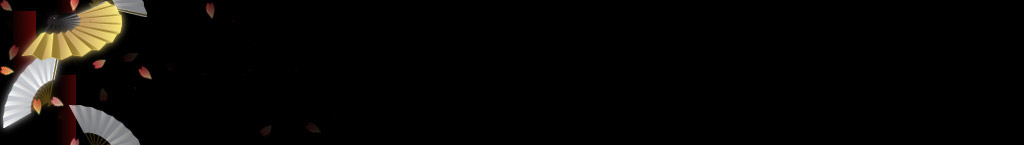
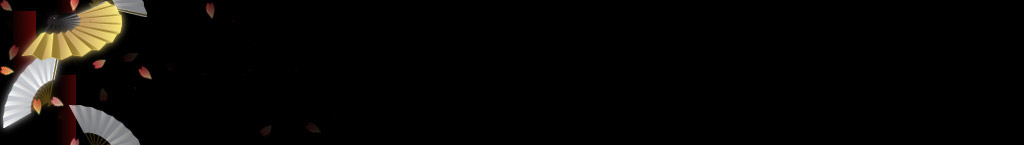
秘すれば…(投稿用)3
三
年が明けた。
果月は年末から大掃除や雑務等で朱雀能楽堂に泊まり込み、年始は内弟子らと供に師範の挨拶回りを行なったりと、正月も瞬く間に過ぎていった。友弘の方も能面師関係の集いなどに招かれ、忙しく動き回っている。この時期、二人が家でゆっくりくつろげるのは、新年会が終わった後といつも決まっていた。そして、とうとう新年会の日がきた。
「今日の新年会、時間が許すようだったら観に行くよ」
友弘が朝、出かける果月に言った。
「いいよ、友弘もまだ忙しいだろ」
「でも、お前が俺の面をつけて舞うのに…」
確かに友弘に自分の姿を見て欲しいと思うが、自分を観る事は、同時に十郎も観るはめになる。去年までは友弘は十郎に会うのを避ける為、わざと他の用事を作って来れなくしていたようだった。しかし、今年は果月が自分の『小面』をつけるので来たいらしい。果月としては複雑な気分である…
「本当に時間があったらでいいぞ。無理しなくていから」
「ああ、分かった、頑張ってな。いってらっしゃい」
「いってきます」
果月は新年会の会場となる『黎明会館』に向かって自転車を走らせた。新年会は市と共同開催している毎年の年始行事で、上演される場所も市民会館の『黎明会館』で二階の大劇場を能舞台に特設して行われるのだ。流派の者はもちろん、関係者や取材陣も大勢招待されている。新年早々の大規模な演能会という事もあって一般客も多く訪れており、見所はいつも満席だ。今年の番組は狂言と日本舞踏をはさんだ三番立てで、『老松』『二人静』『望月』という演目が組まれた。特に『二人静』は最高の能楽師と名高い近江十郎に、最近頭角を現し始めてきた小鳥遊果月がどこまで迫れるかで注目されていた。
控え室で着替えていると、武が顔を出した。
「よう果月、大丈夫か?緊張してないか?」
「ああ、別に」
「本当に大丈夫か?無理して隠さなくていいんだぞ」
「どういう意味だ……?」
「いや、だってあの十郎先生と相舞の『二人静』だろ。実力の差がはっきりとでるし…って、いやお前なら大丈夫だよな、睨むなよ〜」
果月に無言で睨まれて武は慌てて言い直す。
「でも、いいよな。あの十郎先生と稽古できたんだからさ」
月華流の能楽師なら誰でも十郎に憧れを抱くのだ。それ程彼の舞は内外とわず高い評価を受けている。指導を請う者も後を立たず、余程の才能あるものか、伝手のある者でなければ彼に稽古をつけてもらう事はできなかった。家長としての威厳ある風格も、名のある父親に劣らない才能も持つ彼は皆に尊敬されている。多少、高慢な言動はあるにしても、実力がともなっているので誰も不平は言わないのだ。
「何回ぐらい合わせ稽古したんだ?」
「申合(もうしあわせ)だけだ…」
申合とはリハーサルの事で、面や装束を着ていない以外、本番とまったく同じに進行する。面は流派にもよるが、本番までつけないのが通例だ。基本的に能役者が面をつける事に『慣れ』をもってはいけないのである。
「またまた、御冗談を〜」
「……………」
「…って…マジなの…?」
「……………」
「おい、それってまずいんじゃないのか?本当に大丈夫なのかよ〜」
果月と十郎は一度も合わせ稽古をしていなかった。果月が近江家の稽古場にいる時十郎はいなくなり、十郎が近江家にいる時は果月の方が来なかったからである。
『二人静』は静御前の霊が憑いた菜摘女と、静御前の霊が同装で相舞をするというものだ。面をつけると視界がほとんど0(ゼロ)になるので、舞のタイミングは稽古をしまくって合わせるしかない。が、二人はお互いそれを拒んだのだ。玄雄には何度も怒られたが、果月は行動を改めなかった。
『どうしても俺と稽古がしたいなら、あいつの方からくればいいではないか』
そう思ったのである。十郎の方も同じ言い分なのだろうが。そのうち玄雄は「失敗して恥をかくのはお前達なのだから、好きにしろ」と諦めた。彼としては申合で懲りて稽古をする気になるだろう、とふんだのである。そして近江家の稽古場で開かれた申合で、果月と十郎は初めて同じ舞台で舞った。その申合が終わった後、玄雄は二人に何も言わなかった。
「果月、もうすぐ出番だ、鏡の間に行け」
「はい……」
玄雄が呼びに来たのですぐに舞台端の鏡の間に行き、武も働きに戻る。そこに十郎はまだ来ていなかった。
「あの近江十郎と相舞とはプレッシャーがきついだろうな」
「ええ、あの若さではね」
見所でのざわめきが聞こえてはいたが、鏡の間で出番を待つ果月は心を穏やかにしようと努めた。心を濁すまい、無心を保とうと、瞳を閉じて座っていた。
「面をつけておけ」
「はい……」
玄雄の言葉に果月は傍らに置いてあった木箱を開けて、面を取り出した。
洋風の仮面はかぶる、という表現をするが、面はつける、かけるという言葉を使う。面によって変貌するのではなく、能楽師と面が一体になる事を理想とするからである。面が人の顔よりも少し小さく作られているのはこの為だ。
友弘の打った『小面』は清楚で美しい。自分がこの面と一体となり、命を与え、幽玄の世界を舞うのだ。そう考えると果月は胸が震えた。『能』は踊るのではなく『舞う』のである。感情を表現するのではなく、心を解き放つのだ。果月は大きく深呼吸してから面をつけた。
『二人静』のあらすじは、神社に使える菜摘女の前に一人の女が現れ供養を頼むところから始まる。神社に戻り、神主にその話をするのだが、話しているうちに疑いの心が生じてきて「まことしからず候ほどに…(本当の事ではないような)」と口にしてしまう。途端に様子がおかしくなり「何、まことしからずとや(なんですと、あんなに頼んだのに)」と口ばしる。静の霊が乗り移ったのである。『静御前』に取り付かれた菜摘女が舞っていると、静御前の霊が現れ、いつしか二人はよりそって舞い、花吹雪にまぎれて消えていくのである。前半はツレである菜摘女が物語を引っ張る。
「何、まことしからずとや」
という言葉によって平凡な菜摘女が、気高い静御前となる。それはツレがシテの位へと変化する瞬間でもある。謡の調子が変わると共に面貌の変化も表現しなくてはならないので、役者の力量が問われる瞬間だ。表面的な変化が大切なのではなく、空間に存在する『間』をいかに結晶させるかなのだ。
『能』はあらゆるものを省略化し、抽象化した舞台である。観客の一人一人が、自分の裡に沸き上がった感情を舞台と一体化させて観る演劇で、個別に自分だけの『能』を創ると言っていい。能楽師は決して感情を爆発させず、蓄積し、心情を表現するのだ。その精神の集中には膨大なエネルギーが必要となる。故に『能』の舞台には静かで深い緊迫感が満ちている。
すべてが沈黙する一瞬、すべてのものが停止する一点、その緊迫を結晶として満たせるか。能楽師はそれができて初めて能楽師足る事が出来るのである。
果月の菜摘女は見事静御前へと変化し、澄んだ緊張感を漲らせてみせた。十郎の『静御前』が現れ二人が相舞すると、見所からはため息が漏れた。『二人静』は「影に形の添うごとく舞え」と言われるが、二人はまさしくその言葉のごとく舞っていたのである。
申合で初めて相舞した果月と十郎であるが、その時、二人の舞は鏡のようにぴたりと合っていたのだ。運ビ(ハコビ※歩く事)の歩幅も歩数もお互い知らないにも関わらず、同じだった。手の角度、身体を動かすタイミングでさえも同じで、度胆を抜かれた玄雄は二人に合わせ稽古をしろ、とはもう言わなかった。見ていた弟子達は二人とも相当稽古をしたに違いないと信じていたが、実際果月と十郎が合わせたのは初めてだったのだ。申合が終わった時、玄雄が
「お前達は美しいと感じる感覚が似ているのかもな」
と言ったので、果月は不快に思ったのだった。
『二人静』が終演すると、次の日本舞踊の準備の為に休憩となった。緊張から解放された観客の感嘆の声があちこちからあがる。
「これは…『井筒』に続いて『二人静』さえも近江家の能役者にとられるぞ…」
「あの若者の実力は確かでしたね」
「十郎殿と相舞してもひけをとらんとはすごい」
皆、次々と感想を語り合っていた。
果月が控え室で面の裏についた汗をぬぐっていると、武がまた顔をだした。
「すごかったな果月、大成功じゃんか」
「……………」
果月は何も言わず、黙々と装束を脱ぎ始めた。
「心配したけど杞憂に終わって良かったよ」
返事はなく、果月は不機嫌な表情を浮かべながら大急ぎで袴姿に着替えはじめる。
「果月?聞いてんのか〜?」
隣で話し掛ける武の言葉は今の果月の耳には届いていない。悔しくて心が乱れて、一刻も早くこの空間から、今の舞台の余韻の残る場所から飛び出してしまいたかったのだ。
「武何してる?『望月』の準備は終わったのか」
「はい、今行きます」
武が去っていったのと同時に、着替えをすませた果月もロビーへ出る。大劇場では舞踊が始まったらしく誰もいない。本当は遠くへ走り出したい気分だったが、完全に姿を消す訳にも行かず、ロビーや階段周りをウロウロして頭を冷ました。少し気分が落ち着くと、一角に展示してあるガラスケースをぼんやり見つめながら考えた。
今日、初めて十郎と同じ舞台に立ち、彼の実力の凄さを実感した。自分の傍らで舞う彼は全てを掌握していた。舞台も囃子方も後見や観客達でさえ彼は支配しており、自分もその中の一人であった。しかも十郎は自分に合わせる為に、いつもより存在感を消していた。菜摘女を圧倒する程の静御前が登場すれば、演目は台なしになる。どれ程美しい音でも回りと波長が溶け込んでいなければ、雑音になってしまうのと同じだ。彼は自分をコントロールして舞台を完璧なものにした。十郎が周りから尊敬され、天才と呼ばれる意味が分かったような気がする。そしてもう一つ、分かった事がある。なぜ、自分と十郎の舞が鏡のようにそっくりだったのか…
「その刀の言い伝えを知っているか?」
後ろから十郎の声が聞こえ、果月は驚いて振り返る。彼が稽古以外で果月に話しかけたのは初めてだったので、果月は他の誰かに対して言ったのかと辺りを見渡した。だが、ロビーには自分達だけしかいなかった。十郎の言っている刀は、今、果月が見ていたガラスケースの中に展示している日本刀の事であろう。
「この地に伝わる伝説の刀だ」
伝説とは、刀鍛冶の娘と結婚する為に、弟子が一晩で千本の刀を打とうとする昔話である。
昔、高名な刀鍛冶師と美しい娘がいた。日頃鍛冶師は
『娘の婿は一晩で千本の刀を打てる者でなくてはならん』
と、口ぐせのように言っていた。ある日、一人の弟子が娘と結婚させて下さいと頼み、夜明けまでに千本の刀を打つと約束する。弟子は誰も覗かぬようにと頼み、鍛冶場にこもるが、好奇心に負けた鍛冶師が覗いてしまう。そこで見たのは鬼に変貌して刀を打つ弟子の姿だった。恐ろしくなった鍛治師は鶏に無理矢理刻の声を上げさせ、夜が明けたようにみせかけた。弟子は間に合わなかった、と絶望し死んでしまうのである。刀は九九九本打ちあがっていた。
地元に住む者なら誰でも知っている話だ。ガラスケースの中には、その弟子の打った刀のうちの一本と言われているものが収まっている。
「果たせぬ約束なら、初めからせねばよいものを…」
果月はカッと頭に血が上って反論した。
「鍛治師が卑怯な真似をしなければ、千本の刀を打ち終わっていたかもしれない」
「それはあくまで仮説だ。どんな言い訳をしようと男は達成する実力がなかったのだ」
「実力を自覚し、わきまえろという意味か?俺に対して言っているのか?」
「……………」
果月は今日の舞台で分かってしまった。なぜ、自分と十郎の舞が鏡のようにそっくりだったのか…
それは同じ心を解放していたからだ。
桜の花びらのただ舞散るだけの様を人々は純粋に美しいと思う。『能』の舞はまさにこれである。感情はなく、無欲の中に宿る純粋な美しさ。だがそれ故に狂気を孕む。『舞う』とは『狂う』事でもある。自分達は、同じ狂おしい程の心を解き放ち、舞っていたからこそあそこまで同調したのだ。
『お前達は美しいと感じる感覚が似ているのかもな』
玄雄の言葉通り、自分達は同じ人を愛しいと想っている。
『この男は友弘を愛しているのだ…』
舞台で十郎の想いが痛い程伝わってきた。彼がどれ程深い心を秘めているのか分かってしまった。彼の『井筒』がなぜあんなにも人々の心揺さぶるのか。『井筒』は愛する人が死してもなお慕い続ける女の舞…
だが果月はそれを認める訳にはいかなかった。友弘をあんなにも傷つけた彼が、苦しい程想っているのを。この男と同じ近江家の血が自分には流れている。同じ人を愛し、同じ想いを胸に秘めて舞う…
『影に形の添うごとく舞え』
では、影は俺か?俺がこの男の影か?
「俺は愛する人を手に入れる為なら千本の刀を打ってみせる」
果月は十郎の前に立ち、言い放つ。
わきまえろ、などと言わせるものか!
「……鬼になってか……?」
「……鬼も蛇にもなれる……」
果月は十郎にまっすぐな熱い視線をぶつけたが、十郎は涼し気な表情であった。
『俺が分かったのだ。こいつが俺の気持ちに気付かない訳はない』
十郎は自分に牽制しているのだ。
果月は彼の脇を通り抜けてその場から離れた。背中に十郎の存在を感じながら、この男にだけは絶対に負けたくない、と心の底から思う。男としても…能楽師としても…
十郎は果月の熱い視線を平然と受けたが、心はざわめいていた。あの瞳は、先日近江家の中庭で向けられていたものと同じ瞳だった。自分に対する憎しみと嫉妬が入り混じった瞳。父親を独占したい子供のものではなく、熱い男の視線だ。愛する人に触れた者に対する憎しみが滲みでていた。そして、今日の舞…あいつは男として友弘を愛している。
「……餓鬼が……」
十郎は死んだ小夜子の亡霊が、また自分の前に立ちふさがった気がして忌々しかった。いつまでも自分に影を落とす彼女の…
新年会は大成功のうちに幕を降ろした。皆は喜びのうちに『黎明会館』の一階に設けられたパーティー会場での宴会に突入した。果月には大勢の雑誌記者がつきまとい、十郎とのツーショット写真が撮りたいなどと言い出されて辟易した。しかし、十郎が
「これから月華流の集会がありますので失礼します」
と、言って玄雄達と出て行ってくれたので写真は免れた。家元や長老達は別の高級料亭で新年会をいつも行っているのである。幹部らがいなくなって、気が楽になったパーティーは大いに盛り上がった。そんな中、ただひとり果月だけがうかない顔をしていた。果月は会場から離れ、奥まった廊下の窓から外を眺めた。マスコミがまだ煩くつきまとってくるし、一人になりたかったのだ。胸に黒い塊があり、いつまでたっても飲み込めないでいるような息の詰まる感触がした。
「果月、どうしたこんなところで?」
武が偶然見つけて話しかけてくる。舞台が終わった直後より、幾分か落ち着いていた果月は武の声に耳を傾けた。
「…ああ…ちょっと気分が悪くてな…」
「大丈夫か?酒の飲み過ぎか?」
「違う…大丈夫だ。すぐに収まる」
「ともかく『二人静』の成功おめでとう。今日のお前はすごく良かったぜ」
「……俺の力じゃない……」
「何?」
「…俺はただあいつの掌で舞っていただけだ…」
「十郎先生の事か?確かにあの方は素晴らしい舞手だけど、彼についていける能力がなければ駄目だぞ」
「……………」
「今日のお前は本当に良かった。前半から舞台を素晴らしいものにしたのはお前の力なんだから堂々と胸はってろ」
武が果月の背中をバンと叩く。果月は気持ちが少し楽になった気がした。
「ちょっと聞いたんだけど、果月、お前朱雀の方に住込もうと思っているのか?」
「ん?ああ…そうしてもいいかな、って考えてはいるんだ…朱雀に住込んだ方が稽古に集中できるかと思ってさ」
「でも、今みたいに家から通っても差し支えないだろう?」
「ああ、玄雄先生も別にわざわざ住込まなくていい、と言ってはいるんだが…」
「お前が家出たら小鳥遊さん一人になっちゃうんじゃないか?」
「……………」
問題はそれなのだ。果月は友弘と同じ屋根の下で暮らすのが苦痛になってきたのである。これ以上彼の側にいたら、自分は何をするか自信がなかった。彼の元を離れた方がいい、と思うが一方で、友弘と離れた暮らしに堪えられるのかも自信がないのだ。自分がいなくなって彼はどんな生活をするんだろう、今、何をしているんだろうか、と一日中気になって仕方がないのでは、とも思う。自分でもどうしたらいいのか分からなくて、実行出来ずにいるのだった。この話は玄雄と須藤にしか話していない。
「会場に小鳥遊さん来てたぜ」
「友弘が?」
「ああ、お前を探してるんじゃないか?こんな所にいたら見つけられないだろ」
「分かった。武、ありがとう」
「おう」
現金なもので、友弘が来ていると知っただけで気持ちが昂る。早く会いたいと、果月はパーティー会場に戻った。広間に入ろうとしたその時、果月は入り口付近で友弘を見つけた。が、綺麗な和装の女性と親し気に話をしていたので、声をかけるのを躊躇ってしまう。
『誰だ?知らない女だ…』
小柄な友弘よりさらに小さく華奢な印象の女性である。歳は友弘より若干上に見えるが、友弘は童顔なので同歳ぐらいかもしれない。
『何話してるんだ…?』
にこやかな表情の友弘に少し腹がたってくる。飛び出して話の腰を折ってやろうかと思うが、お客だったら水を差すのはまずい。果月はとりあえず身を隠し、話が終わるのを待った。女性が友弘と離れるのを確認してから声をかける。
「友弘、来れたのか?」
「果月、どこ行ってたんだ?会場にいないから帰ったのかと思ったよ」
「ちょとね…舞台観れたのか?」
「途中からだったんだけど、お前の『二人静』には間に合ったよ。とっても良かった…感動したよ」
「ありがとう」
十郎にも感動したのだろうか、とふと思う。
「それよりさっき話してた女の人誰だ?」
「え?…え、そんな人と話してたかな…」
友弘の目が泳いでいる。
「…さっき話してたろ…」
「あ、えと…道…聞かれたんだ」
市民会館の中でどうして道聞くんだ?という疑問は取りあえず飲み込む。友弘は嘘が下手だ。
「何かを注文した客じゃないのか?」
「そうそう、お客さんだ。帯留の発注を受けたんだ」
「……………」
友弘は能面の他に木彫りの帯留や、着物の絵柄など描く仕事などもやっている。能面だけではどうしても需要が足りず、生活していけないからだ。先程の女性もその客かと思ったが、どうやら違うようである。友弘は何かを隠しているのだ。
『一体何を隠しているんだ?』
果月は気持ちがまた重く沈んでいくのを感じた。
*
後日、果月はこの女性を偶然見かけた。季節は如月に入り、寒さもいっそう増している頃だった。果月は足袋を買いに街の呉服店を訪れた。そこは友弘に着物の絵柄など発注してくる長い付き合いの店で、果月が来るとすぐ奥にある畳の間に上げてくれた。薦められるままにだされた茶など飲んでいると、二人連れの女性客が店に入ってきた。果月が何気なく目をやると、女性の内一人はあの新年会の時に友弘と話していた人だったので驚いた。悪い事をしている訳でもないのに、咄嗟に背中を向けてしまう。頼んでいた仕立てを取りに来たようで、店員が「少々お待ち下さい」と店の奥に引き返していった。残された女性達はお喋りを始め、果月にも小さくではあるが聞こえてくる。
「例の縁組みどうするつもりなの?息子さんいくつだっけ?」
「二十歳よ。しっかりした子みたいなんだけど…」
「大丈夫なんじゃない?二十歳なら思春期も過ぎているし、親に甘える歳でもないでしょうに」
「確かにね…でもとっても仲がいいらしいわ。引き裂くような形になってしまうんじゃないかしら?」
「そんな大袈裟な。直接会ってみたの?」
「まだよ。ちょっと怖いし、小鳥遊さんから話してもらった方がいいでしょ?会うのはそれからにしようかと…」
「そうね、それからの方がいいかもね」
店員が着物を持って戻って来たので会話はそこで終わった。二人は店を出ていったが、話の内容を聞いていた果月は愕然とした。
――縁組み?引き裂く形?俺に会う?――
『……友弘…まさか…再婚……?』
今までに何度か見合いの話が友弘に持ち込まれたが、彼は断り続けていた。果月という子持ちであったし、まだ小夜子を想っていたからである。仲介となった人も、裕福でなく息子もいる男では相手が可哀想だと考え、無理に進めてこなかった。しかし、果月はもう成人したし、朱雀の方へ住込む事になったら友弘は一人である。
玄雄が友弘が一人になるのを見越して紹介したのか?再婚相手の方も子供なしならば、と承知したのではないだろうか?
果月は胸を高鳴らせながら考えた。
『いや、そんな筈ない…だって友弘はまだ母さんを…』
では、なぜ新年会の時、話してくれなかったのか?
『俺の住み込みが決まってから話すつもりだとか…?』
不安な気持ちが膨らみ、いてもたってもいられず、足袋を持つのも忘れて果月は家に向かって駆け出していた。家に戻ると、友弘は作業場の部屋にいた。バクバク鳴る心臓を抱えて、果月は部屋に入っていく。
「おかえり果月。早かったな」
部屋は変わらず檜の清々しい香りが漂う。友弘の優しい香りに果月は胸が痛くなった。
『もし、本当に再婚する気だったら…』
絶対に許すものか、と果月は意気込んで友弘に声をかけた。
「…友弘、聞きたい事があるんだ…」
「なんだ?そんな怖い顔して?」
そう言いつつ、ちっとも怖がっていない友弘の不思議そうな表情に、果月は取り乱しそうになる。
「…新年会で女の人と会ってたろ?」
「え…?う…うん…」
友弘の視線が逸らされる。
「あの人…帯留注文した客って言ってたけど、違うだろ?」
「…どうして、そう思う?」
「…縁組ってなんだ……?」
友弘は少し驚いたように果月を見上げたが、小さく息をついた。
「そうか…知ったのか……」
「じゃあ…本当に……?」
「一応話は頂いたけど……」
果月はあまりのショックで目眩がした。今までならすぐに断っていたのに…
本当に友弘が再婚するのか…?この家で俺以外の誰かと暮らすのか?誰かとご飯を食べたり、他愛無い話をして笑うんだろうか?
想像して果月は吐き気がこみあげてきた。絶対に堪えられないと思った。もし、そうなったら自分はどうなるのか予想もできない。
『絶対に厭だ……』
いっそ…今ここで…友弘を自分のものに…
そんなどす黒い欲望が沸き出していた。
「お前が嫌なら断るつもりだよ」
「え?」
友弘の言葉に、爆発寸前だった果月は夢から覚めたようにハッと気がついた。
「ど、どうして俺の判断で決めるんだよ…」
「だってお前が嫌なら意味がないだろ?」
「なんで…俺にもこの家でいっしょに暮らせって言うのか?」
「え?」
「絶対に厭だぜ…今まで俺達は俺達だけで上手くやってきたじゃないか!なんで今さら誰かをいれなきゃいけないんだよ!」
『俺の目の前で誰かと暮らしている姿をみせつける気か!』
「果月…お前勘違いしてるのか?」
「勘違い!?何が?」
「もしかして俺が再婚するとか思ってる?」
「……え?…違うのか……」
「違うよ」
「……だって…縁組って…」
果月はパニックに落ち入りそうだった。
『どういう事だ?再婚するんじゃないのか?』
「……養子縁組の事だよ」
「養子?」
「…ああ…あの人は能楽師の名門の奥様なんだが、跡継ぎがいないそうなんだ。それでお前を養子にしたいっておっしゃってきたんだよ」
「俺を?!」
あまりに思い掛けない言葉で、果月は呆然とした。
これは玄雄から紹介された話で彼はこの話に乗り気だった。自分が元気なうちはいいが、自分が亡くなった後、近江家の配下にいたままでは果月はろくな役をもらえないかもしれない、と心配しているのである。なんとか十郎と打ち解けて欲しいと願っているのも、果月の将来を心配すればこそなのだ。しかし、養子としてちゃんとした能楽師の名門の家に入れば、果月の身は安泰だ。友弘も果月にとっていい話だと分かっていたが、淋しさからなかなか言えずにいたのである。けれど、自分達の間にある絆は決して消えない、と信じて友弘は覚悟を決めた。
「どうする?一度会って話をしてみるか?」
「……でも……」
いきなりの展開で果月は頭が回らなかった。感情があっちこっちに揺さぶられて、どう対処していいか分からない。心と身体がちぐはぐになっている気分がする。さっきまで怒りや憤りが渦巻いていた心に、スコーンと白い空間が出来たような気分である。
「奥さんは優しくていい人だったよ…俺もお前の将来を考えるとその方がいいんじゃないかって気もする…もちろんお前が嫌じゃなければだけど…」
「友弘…?」
「俺との暮らしじゃろくに着物の仕立てもできないし、足袋買うのだって気をつかってるだろ?何のきがねもなく稽古出来るんだから、いい話だと思うよ…」
友弘は昔ながらの職人気質で、絶対に納得のいく仕事しかやらなかった。創るものは手作りの一点もので、どれもみな素晴らしいが、値段も高くなるので発注はあまりこない。大量生産する着物のプリント図案などやれば、コスト的にも時間的にも楽だが友弘は生活がどんなに苦しくともしなかった。温和で物事にうるさく言わない彼であるが、仕事に対してだけは真摯で頑固なのである。
しかし和装は何かとコストがかかる。質を落とせば安価なものはあるが、やはり能楽師として整えなければならない最低限のラインというものはある。大学に進まなかった果月はバイトでもしようかと思ったが、友弘に反対された。時間はすべて稽古の為に使うべきだ、と主張したのである。なによりも仕事に対して頑固な友弘はバイトをしながら稽古をするという、いい加減な姿勢が厭だったのだ。果月としても本当は稽古を疎かにしたくなかったので、友弘の言うとおりにした。そんな訳で二人の生活に余裕はなかった。
「俺は…少し淋しいけど大丈夫だ…気にしなくていい」
「友弘、俺は……」
養子なんかに行く気はない。友弘と暮らして厭だと思った事など一度もない。そう言おうとした果月だったが、ふいに頭の中にある考えが浮かんで言葉を飲んでしまった。
『もし、俺が養子縁組したら友弘と親子ではなくなる…彼の息子ではなくなるんだ…』
心に出来た真っ白な空間に、果月は淡い期待を描いてしまった。だが、次の友弘の言葉でその期待は無惨に打ち砕かれた。
「お前と俺とは離れて暮らしていても、いつまでも親子だろ」
果月はナイフが突き刺さったような衝撃を胸に感じた。大きな風穴が開き、血が吹き出す。
「名字が変わっても、いっしょに過ごした時間は消える訳じゃないし、果月はずっと俺の息子だと思ってるよ」
「……なん…だって……」
「だから果月は自分の事だけを考えて決めれば…」
「…なぜ…息子でなきゃいけないんだ……」
「え……?」
駄目だ、駄目だ、と果月は心の奥で警告をするが、一度血ととも吹き出した言葉は引き戻す術をもたなかった。
「……俺と友弘は…血が繋がってないんだ…赤の他人だろ…」
「果月……?」
「どうして、いつまでたっても息子でなきゃいけないんだ!」
果月は悲鳴をあげた。友弘は驚いて果月の顔を見つめる。悲し気で呆然とした表情だった。
『もう、駄目だ……』
感情の押さえが効かない。果月の裡に封じてあった想いが一度に噴き上げてきている。知られてはならないと誓った己の醜い心も…
果月は手をのばして友弘を思いきり強く抱き締めた。
「…果月…?どうした……?」
友弘が背中をポンと叩く、その仕種にも身体が熱く反応する。
「……好きだ……」
「…ん……?」
「……俺は…友弘が…好きだ……」
「…そ…それは…俺も……」
「……愛している……」
「……え……?」
友弘は今自分を抱き締めている人が誰なのか分からなくなった。厚い胸板に、自分の腰に回された力強い腕、耳もとで囁く掠れた声。以前にも、誰かにこんな風に抱き締められた記憶が蘇り、友弘の背中がぞくりとする。
「…あ…あの…果月…ちょっと、離し…」
友弘が身を捩って果月の腕から抜け出そうともがくが、果月は彼の顎を掴んで上に向かせると唇を重ねた。
『……え……』
友弘は何が起きたのか分からなかった。ただ、果月の顔が見えないくらい近付いてきて、いきなり息ができなくなって、唇の間にぬるりとした感触が入ってきて…
「!」
何をされているのか理解した友弘は、果月の身体を突きとばして、無理矢理身体を離した。反動で友弘は後ずさり、背中が壁につく。
『…な…なに…何が起こったんだ…?』
友弘の頭は混乱していた。唇を右手で覆いながら、目の前に立っている男を見つめる。
『…果月…じゃない…のか…?』
自分より大きな身体、抗えない程強い腕を持っている目の前の男は…
あの夜、淋しくて自分の部屋に来た果月じゃないのか…?いっしょに布団に入り、抱き締めたあの小さな男の子は…?目の前にいる背の高い男と同じ果月なのか…?
六年前、力で自分をねじ伏せた男と重なり友弘は悪寒を感じる。背後は壁しかないと分かっているのに、無意識に後ずさってしまう。
「…俺が…怖いのか……?」
「……え……」
果月の声に友弘の身体はビクリと震えた。
「……どうしようもないんだ……」
「……な、なに…が……」
「……俺は…友弘を…愛してる…」
友弘は恐怖を感じた。目の前にいる果月の瞳が、六年前に自分を犯した十郎と同じ瞳をしていたからである。
『……嘘だ…違う……』
心は必死に否定しようとするが、脅えている自分がいる。容赦なく果月の言葉が耳に食い込んでくる。
「ずっと、ずっと好きだったんだ…一人の人として、ずっと愛してた!」
「……やめ……」
「いつも抱き締めたいって思ってた!口付けたいって思ってた!」
「やめろ、果月!」
友弘も悲痛な叫び声をあげた。
「……何言ってるんだ!俺は、俺は、お前の父親なんだぞ!」
「友弘を父親だなんて思ってない!」
「……え……」
友弘の泣き出しそうな表情が目に入り、果月の胸は痛むが止まらなかった。
「自分を陵辱する夢を見るような息子が欲しいのか?!」
「やめろ!」
友弘は耳を塞いで背中を向ける。その肩は震えていて六年前のあの時のように泣いていた。
「……やめてくれ……」
「……友……」
「……聞きたくない……」
友弘の身体は壁に伝ってくずれ落ちた。耳を塞いだまま床に蹲る。彼の姿を見ていられなくなった果月は、走りだして家の外に飛び出していった。果月の足音を聞きながら、友弘はどうする事もできなかった。ただ、哀しくて、淋しくて涙が溢れる。頭がいっぱいで、胸が苦しくて何も考えられなかった…
なぜ、果月はそんな事を言うのだろう?自分達は仲のいい親子だったのではないのか?そう思っていたのは自分だけだったのか?
――父親だなんて思ってない――
果月の言葉が心と耳に痛みもって響いてくる。自分達の間には家族の絆があると信じてきたのに…
『俺の一人よがりだったのか…?』
いつの間にか一人の男に成長していた果月に初めて気づく。あんなに背が高くなっていた事も、力強い腕をしていた事も友弘は気付かなかった。自分の中の彼はあの10歳の果月のままだったのだ。
いつからあんな熱い瞳で自分を見ていたんだろう…?小さな果月はどこにいってしまったのだろう…?
目の前にいたのは、苦し気に愛の告白をする一人の男だった。あの時の十郎と同じように。六年前の出来事を再び体験しているようだった。怖くて身体が硬直する。心が悲しみで満ちていく…
果月の告白を聞いて友弘は初めて彼を怖いと思った。