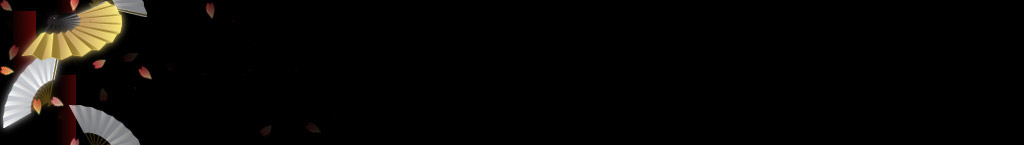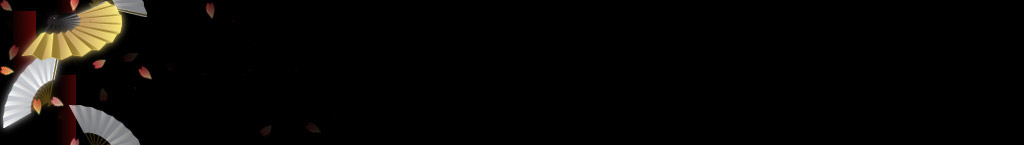
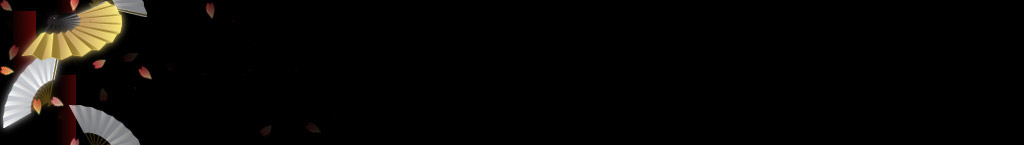
秘すれば…(投稿用)4
四
果月が家を飛び出してから一ヶ月が過ぎようとしていた。
あの日の夜、須藤から果月が朱雀能楽堂に来ていると連絡をもらい、とりあえず友弘はほっとした。須藤は何回か電話をくれたらしいが、飛び出して行った果月を探して外に出ていたので家にはいなかったのだ。やっと連絡がつき、友弘がそれを知ったのは日付けが変わろうとしていた時刻だった。詳しい話はしなかったが察してくれたようで、須藤は何も聞かずしばらく果月を預かると言ってくれた。友弘はキッチンで遅い昼食を食べながら、静まりかえった部屋を見渡した。
『静かすぎる…』
果月と共に暮らした日々の思い出が次から次へと蘇り、友弘はせつなくなる。それに、一人で食べる食事がこんなに味気のないものだったなんて…見慣れた室内がやけに殺風景に感じてもの哀しい。小夜子と三人で住んだのは二年間だけ。そのあとの10年間は二人で思い出を刻んできた。笑って、怒って、果月が子供の頃は時々喧嘩もしたりして。もちろん、次の日にはお互いケロッと忘れて仲直りするのだが。そんな当たり前の家族の生活をいつも夢みてきた友弘は幸せだった。
胸が締め付けられるような痛みを覚え、振り切る為に立ち上がった。ほとんど食べないまま片づけを始める。これからどうしたらいいのだろう…
『もう元には戻れないのか…?』
いや、そんな事はない、きっと何か方法がある筈だ。果月と会ってきちんと話し合えば…でも何を話せばいいんだろう…?
自分が果月を大切に思っている事や、今までの思い出を語り合うのか?息子として大切に思っていると告げるのか?だが、果月はそれを拒んだのだ。息子として友弘が再び接すれば彼は苦しむ。では、一人の男として彼を見た時、自分はどう思っているんだろう…?
考えようとした友弘だったが、抱き締められた時の果月の強い力を思い出して身体が強張る。
『……怖い……』
自分の裡に潜む何かが変わっていってしまう気がして友弘は怖かった。どうしたらいいのか。この一ヶ月、どれだけ考えても堂々巡りで、いい考えなど思い浮かぶ筈もなかった。
もう戻れない、また一人になるのか…
友弘の胸がまた痛み、思わず手をあてる。少し落ち着くと小夜子の位牌が置いてある和室に入り、遺影と位牌の前に正座して心の中で彼女に語りかけた。
『小夜子さん、俺は果月の父親になるって約束したのに、駄目だったみたいだ…ごめん…』
父親……
果月にとって自分は父親になれなかった。でも、自分は果月を息子だと…
本当にそうなのだろうか?自分はいつも彼を息子として見ていたのだろうか?友弘は小夜子の遺影を見つめ続けていた。そして、ある事にふと気付く。
『え……?』
確かめる為、友弘は隣接してある作業場に向かい、保管している小面を二つ取り出して見比べた。一つは10年以上前に打った小面で、小夜子の面影が色濃く反映されている。もう一つは二年前に生徒への見本として打ったものである。早川に指摘されてから友弘は面を打つ時、常に無心であろうと心がけた。しかし、時折無意識に自分の心を反映させている面を打ってしまう時がある。この面も小夜子の影を写してしまったと思ってきたのだが。
『……違う……』
二年前に打った面に写っているのは小夜子ではない。彼女に似た他の誰かである。
『……あ……』
愛しいと想っているものを無意識に写してしまう…
『……なんて事だ……』
友弘は自分の想いに気付き、胸が苦しくなった。感情が込み上げてきて、瞳から涙が溢れる。
『…俺は……果月を……』
ばかな…そんな訳ない…あってはならない事だ…自分達は親子で、果月は小夜子の子で…
友弘は自分の想いを必死に否定した。元に戻るのが一番いいのだ。仲の良い親子ならずっといっしょにいられるのだから。果月もいつか諦めてくれるだろう…
そう自分に言いきかせながら、決して元には戻れないと友弘は心のどこかで気付いていた。
近江家での稽古を終えると、果月は玄雄に呼び出された。今まで聞いてこなかったが、友弘との仲違いの理由を問うてくるだろうと果月は察していた。
「まだ朱雀の方で寝起きをしているのか。一時的なものとして許可したのだぞ」
「…申し訳ありません……」
「須藤がしばらく様子を見ようと言うので黙っていたが、もう一ヶ月が過ぎようとしているぞ…なぜ、家に戻らん?」
「……………」
「友弘と何があったのだ?例の養子の件で彼と揉めたのか?」
果月は静かに首を振った。
「本当にか?」
「……はい……」
きっかけではあったが原因ではない。
「なんにせよ、お前が悪いんだろう、意地を張らずに家に戻れ。彼は黙って許してくれる筈だ。私から彼に話そうか?」
「……いいえ……」
「では、どうするつもりなのだ…?」
「……養子の……話を……」
「ん……?」
「……俺を養子にしたいとおっしゃっている方とお話させて下さい…」
「引き受ける気か…?」
「お会いしてから決めたいと思います…」
「分かった、先方さんと連絡をとって日取りを決めよう。友弘も同席させようか?」
「いいえ!」
果月が大声をだしたので、玄雄は一瞬驚く。
「……俺だけで……」
「…分かった。私はいい話だと思うがな」
「…はい…ありがとうございます…」
部屋から出た果月は重い足取りで廊下を歩いていた。
『これがいいのだ…養子となって他の家に入って、友弘と離れるのだ…』
もう家に帰れないのだから、この話を受けて二度と友弘に会わないようにすれば、彼を傷つける事はあるまい。玄雄には「会ってから決める」と言ったが、果月の心はほぼ決っていた。想いを吐露した今、友弘と普通に暮らすなど出来なかったから。果月は叫びそうになる気持ちを必死に押さえた。どうして言ってしまったのだろう?あの時、心が揺れ過ぎて自制がきかなくなっていた。胸が痛くて、どうしたらいいか分からなくて…自分の気持ちに気付かない彼を滅茶苦茶にしてやりたかった。あの日、抱き締めた友弘の身体は、腕の中にすっぽりと入ってしまうくらい小さかった。腰も細くて、簡単に押し倒せそうで…
あの時、友弘が床に蹲った姿を見た時でさえ、震える小さい背中に凶暴な想いを抱いたのだ。六年前の十郎の事を知らなければ、襲い掛かっていたかもしれない。彼の感触を知ってしまった今、次に会った時は止まらないだろう。
『彼を守ろうと決めていたんじゃないのか?その自分が傷つけてどうする?これではあの男と同じじゃないか、最低だ…』
自分の醜さにとことん落ち込み、果月は深くため息をついた。孤独とあまりに大きな喪失感が果月を苛み続けた。吹き出した血は止まらず、今も流れ続けている。
『よく、立ってられるな…』
果月は自分をそんな風に思った。ふと、顔をあげると反対側の廊下から十郎が歩いてくる。果月は弱っているところを見られたくなくて、背筋を伸ばして彼を睨み付けた。十郎は一度も目を合わさず無言で通り過ぎる。相変わらず自分を無視している彼だが、何があったか気付いているような気がする。もしかしたら、今の自分の心情を一番分かっているのは彼かもしれない…
家を飛び出した当初、果月は稽古に身が入らず、何度も玄雄と須藤に叱責された。そんな時、十郎の視線を感じ、灰と化していた心に火がついたのである。彼にだけは負けたくない…
闘志から気力を奮いたたせ、なんとか稽古には集中できるようになった。しかし、稽古が終わればまた現実を思い出して落ち込むという事を繰り返している。今も、十郎が通り過ぎた後は気が抜けてまた肩を落としてしまう。皮肉な事に、十郎への憎しみが今の果月を支えていたのであった。
その日の夜、果月は使いを頼まれた帰り道をトボトボと歩いていた。最近は春が近付いたせいか、夜でもさほど寒くないが、果月の心は寒い風が吹きすさんだままである。友弘と最後に並んで歩いたのはいつだったろう。ほんの一ヶ月前の事が大昔の出来事のように思えた。軽くため息をつきながら歩いていると、前方に友弘の姿がいきなり飛び込んできて息が止まった。
友弘も驚きの表情をして自分を見つめたまま固まって立っている。一ヶ月ぶりに見る彼は少し痩せたように感じたが、変わらずに愛しい人だった。心臓の高鳴りがガンガンと耳に響き、口から飛び出るのではないかと思うぐらい跳ねている。
『…駄目だ……駄目だ……』
今、彼と会ってはいけない……!
裡からせり上げってきた激しい歓喜に飲み込まれまいと、果月は後ろを向いて走り出した。
「…あっ…果月……待っ……!」
友弘の声が後ろから聞こえるが足は止まらない。道路に飛び出し、反対側の道に逃げようとした。
「危ない!」
「え!」
横から猛スピードのトラックが迫っていた。果月は咄嗟に後ろに飛び、地面に転がりながらもなんとかトラックを寸で躱す。
「気をつけろ!」
トラックの運転手が罵倒を浴びせながら去っていく。
「大丈夫かい、あんた」
「はい……」
周りの人が心配そうに声をかけてくれる。地面に転がった果月が羞恥心を感じつつ起き上がった時、誰かに腕を掴まれる。
「え……?」
腕を掴んだのは友弘だった。真っ青な顔をして身体が微かに震えている。
「……おい…友弘……」
果月の心臓はますます激しく高鳴る。友弘に掴まれた腕が熱を帯び、それが全身にゆっくりと広がってくるようだ。押さえがきかなくなる前に彼から離れなければ…
「……離せ……」
「……………」
果月はできるだけ友弘を見ないようにして声をだした。だが、友弘は掴んだ腕を離さなかった。
「……おい……」
「……………」
その時果月は掴んでいる友弘の手が震えているのに気付いた。ちらりと彼を盗み見ると様子がおかしい。
「……友弘……?」
「……………」
真っ青な顔色は元に戻らず、震えも止まる気配はない。なにより瞳が何も見ていないようにうつろなのだ。いくら声をかえても聞こえていない様子で果月は困った。周りの人々もじろじろと見ているので、仕方なく家まで連れて行く事にした。
玄関で離れよう……
そう思って腕を掴んだまま離さない友弘を、引きずるように家に連れて帰る。だが彼の様子はまったく変わらず、本気で心配になった果月はそのまま家の中に入った。居間で友弘の前に立ち、声をかける。友弘の顔を見るのが怖くて道中はできなかったが、彼の尋常でない様子に不安がつのったのだ。
「友弘、大丈夫か?」
顔を覗き込んで声をかけると、うつろだった彼の瞳が少し動く。
「……あ……」
「……友弘……?」
「……果…月……」
潤んだ瞳に自分の姿が映ったのが見えると、果月は腕を無理矢理振払い、彼から離れた。飛び出そうとする凶暴な想いを必至に押さえる。
「……怪我…ないのか……?」
震える彼の声を聞いて、これ以上いっしょにいてはいけないと思う。咄嗟に自分の部屋に逃げ込み、一刻も早くこの家を出なければ、と思うが、あんな様子の友弘を置いていくのが心配だった。
『どうすればいい…』
電気も付けずに、暗い室内を熱い想いを持て余してぐるぐる歩く。すると、襖が開き、救急箱を持った友弘が入ってきた。廊下から入ってくる光で顔色がまだ青いのが分かるが、瞳はうつろでなく震えも止まっているようだった。
「……な…んの用だ……」
「…怪我…してる……」
友弘が指差した肘を見ると、少し擦りむいていた。
「……たいした事ない……」
「……駄目だ……みせて……」
「……出て行ってくれ……」
「……手当て…しないと……」
果月はだんだん腹がたってきた。ほんの一ヶ月前に言った自分の言葉を覚えていないのだろうか?自分が今、どんな想いを押し殺しているのか彼はまるで分かっていない。どれ程彼を想っているか、どれ程苦しいか…
「いい加減にしろ!とっとと出て行け!」
電灯のスイッチを押そうとしていた友弘の手が止まる。
「いっそトラックに牽かれて救急車で運ばれるぐらい重症になれば良かったよ!」
そうすれば、今、こんな苦しい想いを抱えて友弘の側にいる事もなかったのに!
吐き捨てるように言った果月の頭を友弘はいきなり叩いた。
「……え……」
痛みよりも驚きで果月は呆然とした。親子となってからの12年間、友弘が果月に手をあげるなど一度もなかったからである。果月だけでなく、誰に対しても暴力的な動作は一切しない彼だった。
「……友弘……?」
「……こ…このばか男!」
「……へ……ばか男……?」
「救急車で運ばれるなんて冗談でも言うな!」
「…ばか男だと…俺がばかなら友弘はなんだよ!この鈍感男!」
「な、なに……」
「そうだろ!一体何年いっしょに暮してきたと思ってるんだ!少しは俺の気持ちに気付いてくれてもよさそうなもんだろうが!」
「そ、そんな勝手な…お前は隠してきたんだろ!気付ける訳ないだろ!」
「ぐ…で、でも少しは察してもいいもんだろうが…!」
「無理言うな!」
「それは友弘が鈍感だからだろうが!」
「鈍感で悪かったな、ばか果月!」
「どうせばかだよ!ばかだから友弘を好きになっちまったんだ…!」
「……………」
「…俺だって…好きになりたくなかった…!」
『なのにどうして…』
「…友弘を好きになっても…どしようもないのに…」
泣きそうな顔をした友弘が果月をじっと見つめる…
『なのに…何故…こんなに好きなんだろう…』
もう、駄目だ……
果月は想いを押さえきれずに、友弘を強く抱き締めた。
「……好きだ……好きだ……」
「……果月……」
果月は友弘を抱き締めたまま激しく口付けた。
「……ん……うん……」
友弘のくぐもった声が聞こえて、果月の欲望は煽られる。後ろにあった自分のベッドに友弘の身体を押し倒し、上から覆いかぶさった。友弘の頬を両手で包み込み、再び口付ける。唇を離して果月は彼の項に噛み付いた。
「……あ……」
友弘の掠れた声に果月は目眩がしそうだった。しかし、どうして彼は抵抗してこないんだろう…?
「……友弘…なんで、抵抗しないんだ…?」
「……………」
囁きながら果月は友弘の服に手をかけた。
「…俺は止めないぜ…好きなんだから抱くぞ…」
「……………」
怖くて顔を上げられなかったが、一向に抵抗も拒絶の言葉もなくて不安になった果月は友弘の顔を覗き込んだ。このままでは本当に凌辱してしまうかもしれない。冷たい言葉や態度で自分を止めて欲しいのに。すると、瞳からぽろぽろと涙を流している友弘の姿が目に飛び込んできた。
「……友弘……」
「……にたい……」
「………え………?」
「…一日でもいい…お前より先に死にたい…」
「……友…弘……」
「…置いていかれるのは嫌だ……」
濡れた声で囁きながら、友弘は確かめるように果月の頬を手で包む。果月は友弘の気持ちを感じて胸が苦しくなった。心臓が激しく高鳴る。
「…友弘…俺はいかないよ……」
「……本当か……?」
「……俺は置いていったりしない…約束する…」
「……本当だな……」
「……ああ……」
友弘は果月の首に震える手を回して抱きついてきた。
「……絶対…本当だな…もう…俺は堪えられない……」
愛する人を失う事に……
友弘の声にならない言葉が聞こえて果月は信じられない程の幸福感に包まれる。友弘の背中に腕を回して彼を強く抱き締めた。
「大丈夫だ…絶対に置いていかないから……」
「……本当に…本当だな……」
「……ああ……」
友弘を安心させる為、果月は何度も頷いた。頬を撫で、唇で涙を拭い熱く口付けると、友弘の果月の首に回した手に力がこもる。果月は友弘の身体から衣服を取りさった。
「……あ……」
果月が友弘の露になった身体を確かめるように、指で、唇で触れていくと、彼は甘い吐息を漏らし始めた。
本当にいいんだろうか…触れてもいいんだろうか……?
だが、熱い想いに突き動かされる果月は止まらなかった。友弘は自分を抱き締めている男の体温を感じて心が震えるのを感じた。あの時、果月の姿を往来で見た時、歓喜して自分の裡で何かが弾けた。それは父が息子に対して抱く想いではなかった。その喜びには甘美があり、ときめきがあり、思慕があったのだ。果月がトラックで見えなくなった時には、無の世界に落ちたのを感じた。暗黒の穴にストンと落ちていく自分を感じたのである。何も、何もない無の世界に…それは小夜子を失った時に感じた孤独の暗闇だった。その時の孤独を思い出して友弘は身体を震わせる。
「……大丈夫か……?」
心配そうな果月の言葉に友弘は小さく頷いた。部屋は真っ暗でお互い何も見えなかったが、気配を察したのだろう、果月は一瞬止めていた手を再び動かした。果月の顔が見えない方が友弘は気持ちが楽だった。恥ずかしくて視線に堪らなかったからである。だが、羞恥心以上に友弘は果月を感じていたかった。彼が離れていかないと、決して独りにはならないのだと確証させてくれるものが欲しかった…
「…あ……う……」
果月の触れている箇所から身体が熱く染まっていく。今、自分を抱いている男の色に染まっていくのだ。
『今、自分に触れている男を…俺は愛している…』
小面に写っていたのは小夜子ではなく、果月の面影だった。無意識に愛しい人の面影を写していて…
一体いつから彼を想っていたんだろう?
もう、ずっと長い間息子ではなく、一人の人として愛していたのだ。けれど、それを認めるのが怖くて、自分の気持ちは息子に対してもつ愛情なのだと言い聞かせてきた。親ならば、息子が結婚しても、ずっと変わらず父親でいられる。離れずにすむ。果月から告白された時、怖くてどうしたらいいか分からなかったが、それは今の関係が壊れてしまうという不安があったからだ。しかし、心のどこかで果月の言葉を甘く感じている自分がいた。暗闇の穴に再び落ちて、友弘は自分が誰を必要としているかはっきりと知ったのである。
「……あっ…そ、そんな……」
信じられない箇所に濡れた舌を感じて、友弘の身体がビクリと跳ねた。周りの空気が水を吸い込んだ時の濡れた重みを帯びる。ゆっくりと、まるで蜜の中に沈んでいくような甘い息苦しさを友弘は感じた。友弘の悲鳴のような声が聞こえるが、果月はやめる事ができなかった。彼の啜り泣く声に欲望を掻き立てられる。もっと彼の身体に触れたかった。恥ずかしいところも、触れていないところなどないくらいに…
どうしようもなく昂っている自分を感じた果月は、友弘の膝を抱え上げ、腰を浮かせる。
「……あ……」
友弘が今から起こるだろう行為に身体を強張らせる。果月の背中に手を回してしがみついた。彼の膝頭が自分の掌にすっぽりと入ってしまうのに気付いて果月の胸は愛しさで溢れた。小さな身体を開いて自分を受け入れようとしてくれる友弘が愛しくて堪らない。
「……友弘……」
「……はあ……う……」
果月は友弘の頬に口付けながら、一つになる為に動きだした。
「あ……!……あう……!」
果月を自分の中に感じて、友弘の裡に切ない嵐が沸き起こる。身体中が熱くて、苦しくて、頭がおかしくなりそうだ。大きな快楽の渦に飲まれていく。
「…はあっ……う…ん……」
激しく揺さぶられながら、友弘は10年前のあの夜を思い出していた。小夜子を失った孤独に震えていた夜。自分のところにやってきた小さな果月を抱き締めて眠った夜…あの夜、自分が彼を抱き締めていたつもりだったが、本当は果月が自分を抱き締めてくれていたのだと気がついた。彼が自分を救いだしてくれたのだ。孤独という名の暗闇から…切なくて、友弘の瞳から涙がこぼれる…
「……果…月……」
「……友弘…愛してる……」
二人の身体は一つになって揺れ、共に悦楽の波に溺れていった。
*
明朝、果月は小鳥遊の家から朱雀へ戻った。今朝の能稽古は近江家で行なわれるので、一旦戻って用意をする為である。夜に電話すると須藤にこっぴどく怒られた。昨日は出掛けたきりなかなか帰ってこないので、心配していたようである。
昨夜から今朝まで、果月は幸せな気持ちで自分の腕の中で眠る友弘の顔をずっと見つめ続けていた。夜明け頃に少しまどろんだだけで、ほとんど寝ていなかったが、気持ちが充実していたので身体は平気だった。友弘は自分を一人の男として認めてくれたのだ。そして、想いを受け入れてくれた。これ以上の幸福があるだろうか…
これまで果月の中にたちこめていた暗雲は無くなり、爽快な青空のように心は晴れわたっていた。愛する人と気持ちが通じ合えた喜びで、どこにでも飛んでいけそうな心地だった。玄関を出て家を振り返り、まだ自分の部屋のベッドで眠っている友弘を想った。
「……いってきます……」
果月は囁き、沸き上がる幸福感を胸に歩きだした。
お昼ちかくになって、友弘はやっと果月のベッドから起き上がった。ベッド脇の机には稽古に行ってくるという、果月の走り書きのメモが残されている。だるい身体をひきずって入浴をすませ、食卓の椅子に座りお茶を飲んでいると、昨夜の出来事を思い出して恥ずかしくなってきた。落ち着かずに椅子の上で膝を抱える。自分はなんて事をしてしまったんだろう…
赤くなって熱を帯びる頬を両手で包み込んだ友弘は大きく深呼吸した。昨夜の自分はどうかしていた。大きな感情に支配されて、止められなかった。改めて考えても自分のとった大胆な行動が信じられない。果月の熱さや、吐息とともに耳もとで優しく囁きかける声を思い出して、友弘は身体を火照らせた。
これからどうなってしまうのだろう…
そんな風に考える友弘だが、込み上げてくる甘い感覚は拭えない。全身が風邪でもひいたみたいに熱く、頭がふわふわしている。身も心も愛されるのがどれ程の事か初めて知った友弘は幸せでたまらなかった。身体にまだ果月の手の感触が残っている。一体いつの間にあんなに逞しく成長していたのだろう…
『子供の成長は早い……』
幼い頃の果月を思い出して少し淋しい気持ちになるが、同時に誇らしい気もした。あの逞しい男が自分を想っている事に…
『ば、ばかか俺は……』
自分が優越感に浸っているのに気付いて、友弘はさらに恥ずかしくなる。椅子の上に抱え上げた足を無意識にバタバタ動かす。
『だ、駄目だ…今日の俺は使いものにならない…』
これからいろいろとあるだろうと予感するが、今だけはこの幸福感に酔っていたくて何も考えないようにした。友弘は自室に戻り夜具を敷いた。行儀は悪いがもう少し眠ろうと思ったのである。身体がだるくてたまらなかったし、微熱もあるみたいだった。それに今日は心が浮きたっていて、何も手につかないだろう。寝間着の浴衣に着替えて夜具に入ろうとした時、玄関の扉が開く気配を感じてドキリとする。果月が帰ってきたのだ。早い帰りに忘れ物でもしたのかと友弘は思った。そしてどんな顔をすればいいのか分からなくて頬がまた赤くなる。
いつものように接すればいいんだ…
友弘は自分にそう言い聞かせて、一度深呼吸をすると廊下に通じる襖を開ける。しかし、玄関からのびる廊下に立っていたのは意外な人物だった。
「…十郎……」
家に入って来たのはスーツ姿の十郎であった。友弘は驚きで頭の中が真っ白になった。十郎がこの家に来るなど小夜子の葬儀以来である。
「…呼び鈴を鳴らしたが返事がなかった…」
「え…そ、そうなのか…」
夢心地でぼんやりしていたので、気付かなかったのかもしれない、と友弘は恥ずかしくて俯く。そんな彼の様子に十郎は目を細める。友弘の前に歩み寄り、乱暴に襟元を大きく広げると、そこに鬱血した赤い痣がいくつもあるのを認めた。十郎の心臓は鷲掴みされたように痛んだ。
「…十郎…な、なにを…」
いきなりの十郎の行動に友弘は狼狽した。
「……あいつか……」
「……え……」
「あいつがつけたのか……」
十郎の言葉に友弘はようやく昨夜の情事の痕が身体に残っていると気付き、慌てて襟元を隠す。頬に朱を走らせる友弘に、怒りが沸き上がった十郎は彼の身体を思いきり突き飛ばした。
「あ……!」
友弘の身体が背後の壁に激突し、十郎は自分の身体を押し付けて動きを封じる。後ろに回した手で友弘の髪を思いきり引いた。
「いっ……!」
髪を引かれたせいで喉がのけぞった格好になった友弘に、十郎は顔を突き付けて詰め寄った。
「あいつに抱かれたのか…」
「……あ……」
「何故だ…どうしてあいつなんだ…」
十郎の燃えるような怒りを感じ、友弘は言葉を失う。彼になんと言えばいいのだ…?戸惑っている友弘の唇を十郎は激しい口付けで奪った。
「…う…うん……」
十郎の舌が友弘の口唇を荒々しく蹂躙する。唇をようやく離すと、友弘は苦しそうに息を喘いだ。身を捩って暴れるが、体格の差に加えてだるさの残る身体では逃れようがなかった。
「…十郎……!」
友弘が怯えた瞳で十郎を見つめるが、彼は鋭い視線を友弘に向けたままである。
「どうしてあいつなんだ…小夜子の息子だからか…小夜子の身替わりにしたのか…」
「…ち、違う…俺は本当に果月を……」
好きなんだ、と言おうとしていた友弘だったが、その言葉は十郎に頬を打たれて消えてしまった。
「俺の前であの男の名前を呼ぶな!」
『……あ……』
十郎の叫びに、友弘はどれだけ残酷な事を言おうとしていたのか気がついた。自分を好きだと言った彼に…頬の痛みがそのまま十郎の痛みのように感じて、友弘の胸は苦しくなる。
「お前は渡さない…絶対にだ……」
「…十郎……」
次の瞬間、友弘は十郎の当て身を鳩尾にくらい意識を失った。崩れ落ちる友弘の身体を十郎は優しく抱きとめた。自分の腕に身を預けている友弘を十郎はじっと見つめる。そっと彼の頬に触れ、自分が彼に激しく飢えていたのを感じた。
『もっと早く…こうしていれば良かった…』
何をとまどっていたんだろう…
愛しい人を捕らえた十郎は幸せな気持ちで友弘を抱き締める手に力を込める。もう、絶対に離さないのだと思った。