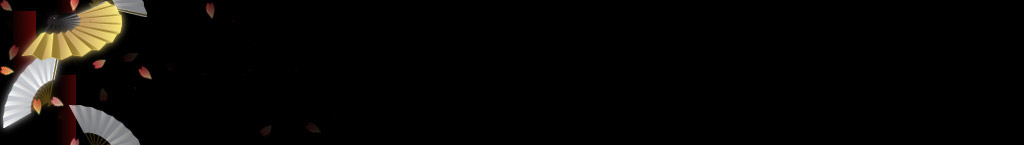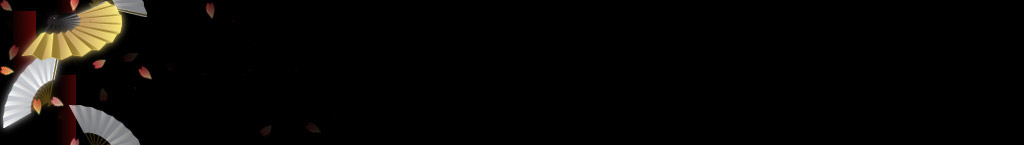
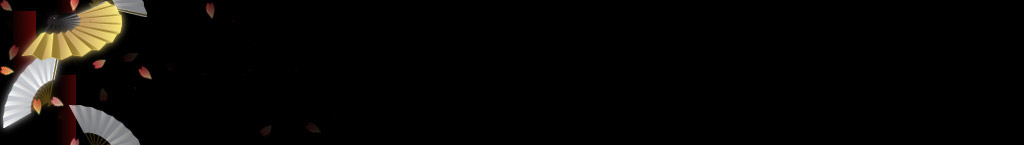
秘すれば…(投稿用)5
五
ごめんね…ごめんね…
『小夜子さん…』
遠い意識の底で友弘は小夜子の声を聞いた。
「……う……」
目蓋をゆっくりと開き、見なれない天井をしばらく瞳に映していたが、何を見ているのか理解するまでに少し時間がかかった。そして、やっと自分がどこか知らない場所にいる事に気がつく。
『…ここは…俺は一体…』
横たわっている身体を起こそうと動かした途端、鳩尾に鈍い痛みがはしる。
「…っ……」
友弘の身体は再び沈み込んでしまった。弾んだ息を整え、首を巡らすと自分は小さな寝室のベッドに寝かされているのを知る。明かりはついていないのでうす暗かったが、初めて見る部屋なのは分かった。
『ここはどこなんだ?どうしてこんな所に…?』
記憶を辿った友弘は十郎が自宅に来たのを思い出す。
『俺は確か意識を失って…あれからどうしたんだ…?』
時間の経過がまるで分からない。取りあえずここがどこか確かめなければ、と友弘は慎重に身体を動かし、ベッドの上に上半身を起こした。身体全体に倦怠感があり、熱があるせいで身体の内は熱いのに肌は寒い。友弘が身震いをしてベッドから出ようと足を動かした時、声をかけられる。
「起きたか…?」
誰もいないと思っていたので、友弘は飛び上がらんばかりに驚いた。声の主を探して首をめぐらすと、ベッドから少し離れた椅子に十郎が座っていたので、友弘は息を飲んだ。
「…長い間眠っていたな…身体の具合はどうだ…?」
「……あ……」
いつから、そこにいたのだろう?もしかして自分が眠っている間ずっといたのだろうか?
いろんな考えが浮かびあがるが、思考が定まらない頭ではなんと言っていいか分からず、友弘は口を噤んだまま俯いた。十郎はゆっくりと動き、ベッドの傍らに立った。
「…熱があるだろ…まだ寝ていろ…」
「……え……」
「喉は乾いていないか?何か持ってこようか?」
「…いや…いい…」
「薬があるから、これは飲め」
と言って十郎はサイドテーブルに置いてあった薬袋からカプセルを取り出し、水差しから水を注いだコップを添えて友弘に差し出した。友弘は黙って受け取り、薬を飲んだ。口調から感じる十郎はいつもの様子で、優し気な空気に友弘の緊張が少し解ける。
「喉が乾いたら冷蔵庫に飲み物が入っているから好きなやつを飲むといい。食べ物も好きにしていいぞ」
「…あ…ここは…?」
「風呂に入りたければ入ってもいいが熱がさがってからだ。タオル類は脱衣所にある」
「…ここは、どこなんだ…十郎…」
「お前のこれからの家だ…」
「……え……?」
「これからここで暮らすんだ。仕事道具も衣服も運びこんでいる。何か足りないものがあったら言え。すぐに用意する」
「…言ってる意味が分からないんだが…」
「お前はあの家には帰さん。あの男のいる所にはな…」
静かだが凄みを含んだ口調に変わり、友弘はまた言葉を失った。
「ここはあるマンションの二階だ。玄関の鍵はカードキーで俺が持っているが、細工がしてあって内側からも鍵がなければ開かないようにしてある」
「……………」
「電話は通じているから、かけたい所にはどこにでもかけられる。出掛けたい時は言え。俺が連れていく…」
「……………」
「では帰るが、何か用がある時は電話しろ」
十郎はそう告げると部屋から出て行った。遠くでドアが閉まり、鍵の掛かる音がやけにはっきりと耳に響く。友弘はベッドの上できりきりと痛む胸を抱えながら膝を抱えた。
十郎が痛々しくて見ていられなかった…
自分をここに閉じ込めるつもりのようだが、長く続く訳がない。いつかは誰かに気付かれて暴かれるに違いないが、その時彼はなんと言うつもりなのか?真実を言えば多くの人が傷つくだろう。十郎の妻である千賀子や、父親の玄雄、母親の妙子。世間に露見すればどうなる事か。本来なら彼はこんな行動をする人ではない。人の上に立つに相応しく、常に周りの様子を見て、人の気持ちを考えている。その為、自分の気持ちを押し殺してきた人で…
彼の歯止めが効かなくなるのは自分の事だけだ。
『…俺がここまで彼を追いつめたんだな…』
六年前の事を十郎が後悔しているのを友弘は知っている。自分が傷ついた以上に彼が深く傷付いているのを。
『…どうして…お前じゃなかったんだろう…』
俺の愛した人が…
彼ならばどんなに良かっただろう。愛して欲しい人に愛されなかった時の辛さを友弘は知っている。育ての親である早川が病院のベッドで亡くなった時、友弘はずっと傍らに付添っていたが、彼は最後まで自分の名前を呼ばなかった。彼の口からこぼれでるのは能面の話ばかりで、彼の目には弟子としての友弘しか映っていなかったのだ。あの時の痛い気持ちを友弘は覚えている。
一言でいい、自分の名前を呼んで欲しかった。一度でいいから自分自身を見つめて欲しかった…
あの時の痛みを今度は自分が十郎に与えているのだと思うと、友弘はやりきれなかった。いっそ彼を愛せたらと思う。しかし、駄目だった。十郎の気持ちを感じてこんなに胸が苦しいのに、心に浮かぶのは一人の男の顔だけ。狂おしい程会いたいと想うのは、愛していると気付いた果月だけなのだ。
稽古を終え、家に帰った果月は呆然とした。友弘の姿がないばかりか、作業場から彼の仕事道具がいっさい消えていたのである。友弘の部屋に入って調べると服もなくなっていた。
『一体どういう事だ!』
今朝からの極楽気分は吹き飛び、果月は再び不安の嵐に叩き落とされたような心地になる。
『友弘はどこにいったんだ…どうして…』
思い当たる場所を探しまくろうと考えた時、電話の呼出音が鳴り、友弘からだと思った果月は急いで受話器を取った。
「友弘か?一体どうし…」
『…友弘はもう帰らない…』
「……え……」
目に見えぬ相手の言葉に果月の全身が凍る。
「…誰だ……お前……」
『彼はこれから別の所で暮らす。もうお前とは会わない…』
「…貴様…十郎だな…そうだろ…!」
『……………』
「友弘はどこだ!どこに行った!?いや、貴様が連れ去ったのか?」
『……そうだ……』
「……てめ……」
果月は怒りの為に自分の身体が熱く燃えるのを感じた。
「ふざけるな!何の権利があってそんな事しやがるんだ!さっさと返せ!」
『友弘に何をした……?』
「…な……何って……」
『…俺は認めんぞ……絶対に……』
果月の心臓が大きく跳ね上がった。この男は知っている…昨夜、自分と友弘が結ばれたのを…
いつ気付いたんだ、という疑問がちらりと頭をかすめるが、果月はそんな疑問よりも、それを知った彼の行動が恐ろしかった。『二人静』の彼がすべてを掌握していた舞台を思い出す。あの時のように今は十郎にすべてを握られている気がした。
「…友弘はどこだ……?」
『…彼は渡さん……』
「…返せ…友弘は俺のものだ…」
『…違う…認めないと言った筈だ…』
「返せ…どこにいるんだ!」
叫ぶ果月をしり目に十郎は電話を切り、残された果月の耳には無情な通話音が聞こえてきた。まるで希望の糸を絶った音のように感じる。
『いや!諦めるものか、絶対に!』
果月は怒りに燃える拳を握りしめた。
次の日、十郎はいつも通りに起き、朝食をすませてから今日のスケジュールを確認した。午前中の稽古の前に、演能会の装束を調べておこうと奥の装束部屋に入る。棚から何種類かの装束を取り出し、畳の上に広げ、紋様や色を簡単に頭にいれた。春は『羽衣』や『熊野』『桜川』といった華やかな演目が好まれるので、装束もおのずときらびやかなものになる。紫地に金糸で鳳凰の紋様のはいった長絹や、藤に扇面、白地に金糸の曾扇の唐織等々、十郎の手元には美しい色とりどりの衣装が広がった。
美しい装束は観る者の想像力をかきたて、『能』という世界へ誘う重要な要素であるが、演目だけでなく演者の力量に合ったものを選ばなくては舞台を台なしにしてしまう。例えば『羽衣』は鳳凰の紋様の入った装束を着ると決まっているが、いくつか種類がある。長絹全体に五色の尾をもった鳳凰が大きく描かれているものがあり、これは『能』という世界を壊さないギリギリの紋様で、着る者を選ぶ装束である。あまりに大胆な構図なので『能』という極めて動きの抑制された舞台では、演者が舞っているというより衣装が動いているという印象をもたれかねないのだ。この装束に飲まれないほどの存在感と表現力をもった演者しか着衣できず、もちろん十郎はそれを着こなせる数少ないうちの一人である。着る者を装束が選ぶ。十郎はどんな装束をも着こなせる才覚を持っているが、他の者はそういう訳にはいかない。どの演目をどの演者が舞うかを見極めて装束や扇を選ぶのだ。十郎が一つ一つ丁寧に見比べていると、戸が開き玄雄が入ってきた。
「装束選びか?」
「はい」
どのような種類があるか確認したので、後は演目が確実に決まってからにしようと、十郎は広げた装束を片付け始める。こういった普通ならば弟子にさせても構わない作業も十郎はいつも自分でやった。
「十郎、お前…あのマンションの部屋をまだ所持しているのか?」
「…お父さんが好きに使っていいとおっしゃったのですよ」
「ああ、確かにな…お前が一人のくつろげる場所として使っていたようだったからな…だが、誰かを住まわせる気なのか?」
昨日、友弘の荷物を運ぶ作業を秘書に手伝ってもらったのだが、そこから玄雄の耳に何か情報が入ったようである。口止めはしておいたが、玄雄に問いつめられて、ある程度答えなければならなかったのだろう。
「あなたのように女性を…ですか…?」
十郎は手を止めて静かに言葉を放った。
「……十郎…昔、獅子の話をしたのを覚えているか?」
「……はい……」
「家長は獅子のようにいるべき場に留まり、楯となって家を守らねばならん。お前はその獅子になるべき人物だ」
「……………」
「獅子が去るのは新しい家長に譲った時だけだ。それまではいかなる事があろうとも、家を守り通すのが使命だ…」
「…分かっています……」
「…獅子に翼はいらん。あったとしても飛び立つ事は許されん…」
「分かっています。だから結婚したのです」
六年前のあの日、婚約を告げられた時、十郎ははっきりと自覚したのである。自分は家長として、月華流を支えていくしか生きる意味を与えられていないのだと。家長はすべてを手に入れているように見えて、実は何も手に入れられないのだと。そんな事は幼い頃より分かっているつもりだった。どんなに見事に舞っても『近江家の跡取りなら当たり前』とみなされるのだ。影で自分が血の滲むような努力をしていたとしても、皆は結果しかみようとしない。反対に平凡な出来の舞を披露しようものなら『跡取りのくせに腑甲斐無い』と非難される。誰もが自分を『近江家の跡取り』というフィルターを通して見るのだ。
友弘だけが自分を『近江十郎』として見てくれる人だった。彼だけは『跡取り』として接してこない唯一の人で、いつしか十郎は彼を心のよりどころにしていた。幼い頃はそれがこんなにも激しい恋心になるなど考えもしなかった…
「婚約を決められた時、家を出た小夜子の気持ちが初めて理解できましたよ」
小夜子の婚約の相手は二十歳も年上の男で、結婚を決められた小夜子は行方をくらましてしまった。彼女の感じた絶望を十郎は初めて知った。あの日、彼女が自分の部屋に来た気持ちも…
自分は家長として生きるのが使命だと子供の頃から悟っているつもりだったのに、実は心のどこかで希望を抱いていたのだ。望めば、手に入れられるものがあるのではないか。自分のもつ翼を広げられる時がくるのではないかと…そんな日は決してこないと、結婚を言いわたされた時にはっきりと分かった。だから、六年前のあの日、友弘に告白し、ここで彼を抱いたのだ。沈黙の悲鳴を身の裡にとどめておくのは不可能だった。自分の叫びを彼に聞いて欲しかった…
「けれど私は小夜子と違い、定められた通り結婚しました。近江家の家長として生きていく決意をしたからです…」
「……十郎……」
「私は誰の期待も裏切った事はありません」
まるで『近江家の跡取り』という型にはまる入れ物のごとく…
「気をもまずともよいのだな…」
「御心配なく」
「……そうか……」
答えながら十郎は冷静な自分を滑稽に思う。なぜこんなにも自分は落ち着いているのだろう?昨日から今までとはまったく違う世界を過ごしているようで、妙に現実感が欠けている。頭の一部が凍ってシンと冷めている感覚があった。しかし、心の裡では燃えたぎっている何かがある。それはずっとくすぶり続けていたもので、いつか自分自身を焼き尽くすのではないかと恐れていたがもう恐怖は感じない。
昨日の朝、稽古場にやって来た果月を見た時、十郎は全てを悟った。果月は先日までの鬱積した表情ではなく、清々しい見がいのある男の顔をしていた。想いに満たされている者の表情だった。
自分の予感を否定したくて小鳥遊家に向ったが、そこで見たのは昨夜の痕跡を身体にのこす友弘の姿だった。結局は自分の予感が適中した事を確かめる結果となり、十郎の裡に押し込めていた激しい想いが吹出した。友弘を連れ去り、玄雄から預かったマンションに無理矢理閉じ込めたのである。
十郎の口元がふっと緩む。自分に歪みが生じているのを自覚していたが、それはむしろ心地よいものだった。堕ちていく事にもはや迷いも躊躇いもなかった。彼といっしょなら…倒錯した甘い陶酔を感じる。
装束を片付け終え、十郎と玄雄はいっしょに部屋を出た。すると廊下の方からなにやら騒がしい声が聞こえてくる。
「はて……どうした……?」
玄雄は首をかしげたが、十郎の察しはついていた。思ったとおり、廊下を乱暴な足取りで歩いてくる果月が目に飛び込んでくる。いきなり上がり込んで来たのを、女中が止めようとしていたらしい。
「申し訳ありません、お止めしたのですが…」
気まずそうに謝る女中を玄雄が下がらせる。
「果月、どうした?随分悪い人相だな」
玄雄の言葉とおり、果月の瞳は充血して目の下には隈ができている。何よりその形相は憤怒のせいで凄まじいものとなっていた。昨夜の十郎からの電話の後、果月は友弘の行き先で思い当る場所を片っ端から調べた。朱雀能楽堂にはもちろん、着物絵付けの職人、能教室の関係者、雑誌出版社の担当にも電話したが、友弘はどこにもいなかった。最後に朱雀能楽堂に帰り、一睡もせずに夜明けを待った。夜中に近江家を訪れても門は閉ざされており、インターフォンで呼びだしても受け付けてくれないと分かっていたからである。そして朝一番に十郎を問いつめる為にここを訪れた果月は、彼への怒りで爆発しそうだった。
「果月、どうしたのだ?」
「……………」
「果月?」
玄雄の声も姿も果月の耳には入っていないようで、その視線は真直ぐに十郎に注がれている。玄雄を無視して歩を進め、十郎に前に立つ。微かに身体を震わせ、憎しみを映した瞳で睨んでくるが、十郎からは一片の動揺も怯えも見えなかった。彼の心はむしろ優越感にほくそ笑んでいた。この男のもっとも大切なものを自分は掴んでいるのだ。長い間、忌々しい存在だったこいつの首をやっと捕らえた嬉々とした気分だ。そして、永遠に離すつもりはない…
「…どこだ…どこにいる…」
「……………」
「答えろ!」
果月が十郎の襟首を掴んだのを見て、慌てた玄雄が側に駆け寄る。
「ど、どうしたのだ果月!やめなさい!」
だが、やはり果月には玄雄の声も姿も入っておらず、目の前に平然とした顔をして立つ憎い男の姿しか映っていなかった。
「お前が俺なら教えるか?」
十郎のその言葉に果月は硬直した。襟首を掴んだ手を震わせ、十郎を睨み付けたまま動けない。そんな果月の手首を掴むと十郎はひねりあげて襟元から離させる。彼の横をすり抜けて廊下を悠然と歩き出した。
「十郎!」
後ろから大声で呼ぶ果月に、殴りかかってくるかと十郎は警戒しつつも振り返える。するとそこにいたのは膝を折り、廊下に手をついて土下座をする果月の姿だった。
「…頼む…返してくれ……」
果月の姿に十郎はしばし我を忘れた。あの男が自分に手をついている。決して自分から話しかけず、会釈もしない男が、友弘の為になら地面に這いつくばってみせるのだ。消えた筈の忌々しいざわざわとした気持ちがせり上がってくるのを感じる。
「……やめろ…立て……」
「……頼む…どこにいるのか教えてくれ…」
「立てと言っているんだ。そんな事をしても俺は教えんぞ」
「……………」
「貴様を認めないと言った筈だ。心は変わらん。だから無駄な事はするな」
「……頼む……」
「無駄だと言っている。二度とこんなみっとない真似はするな!」
吐き捨てるように叫んだ十郎は、今度こそ振り返らずに廊下を歩き去った。こちらに向かってくる果月を見た時の優越感はもうなかった。着物に小さなシミを見つけた時のような胸の悪さがあったが、一瞬、羨望にも似た気持ちが心を走りぬけもした。友弘の為にあんな簡単に膝をつき、自分の弱点を惜し気もなくさらし、自分にはできない事を簡単にやってのける彼に。
『…羨むだと?ばかな……』
優位なのはこちらであり、すべてを掌握しているのは自分なのだ。それなのに、何故あの果月の姿を見ただけでこんなにも心が乱れるのか。友弘に何も言えなかった自分を十郎は思い出していた。愛の告白も、真実も語れなかった自分を。
廊下に残された果月は全身を震わせていた。遠ざかる十郎の足音が手をついた床を通して伝わってくる。怒りや憎しみよりも、二度と友弘に会えないのではないか、という恐れと哀しみに心が張り裂けそうだった。その恐怖から逃れる為なら土下座でもなんでも出来た。自分との関係に後悔して友弘が自ら出ていったのではあるまいか、という不安もあった。頭を下げた状態なので、瞳に涙が溢れ、視界がぼやける。
「…果月…一体どうしたのだ?」
玄雄が心配そうに傍らに膝を折り、声をかけてくれるが、果月は何も答えられなかった。友弘の笑顔が脳裏を横切り、胸が苦しくて息が詰まる。十郎の吐き捨てた言葉は果月に絶望を与えていた。十郎が何をするかなんて想像もしていなかった。しかし、今、現実となって自分の目の前で起きているのだ。
自分が十郎だったらどうする?誰かが友弘を手に入れようとしたら?
おそらく自分が一番理解できるだろうその答えを、果月は恐ろしくて考えまいとした。涙で霞んだ視界が沼の底のようにどす黒く染まっていく。持って行き場のない恐怖と哀しみに苛まれ、無意識に果月は木の床に爪をたてていた。自分の胸を掻きむしる代わりに…
*
友弘がマンションに連れてこられてから一週間が過ぎようとしていた。そんなある日、玄雄から電話があった。
「お義父さん……」
『…友弘…このマンションに住んでいるのはやはりお前だったのか』
玄雄の口調には微かに不安が漂っていた。何故この家の電話番号を知っているのかと、友弘は不思議に思った。
「どうしてお義父さんがここの電話を…」
『このマンションは元々私のものだ。ある人物に貸していたのだが、その人が亡くなったので十郎に譲ってやった』
「……そうですか……」
『…小夜子の母親を住まわせていたのだ…』
「……え……」
『小夜子と母親の妙子は血が繋がっていないと知っているな?』
「はい、結婚する時小夜子さんから聞きました…」
その時、妙子の小夜子と果月に対する冷たい態度に納得がいったのである。妙子の産んだ子は十郎だけで、小夜子と十郎は異母姉弟だったのだ。
「しかし、小夜子さんの母親は、子供だった彼女を近江家に預けてから行方知れずと聞きましたが…」
『そうだ…あれは小夜子を置いていなくなってしまった。だが、果月という孫ができたので伝えたいと思って探していた。しかし、やっと見つけた時は不治の病でな…』
「……………」
『生活は苦しく治療費もままならない状態だったので、せめて最後の時ぐらいは心穏やかに過ごしてもらいたいと思い、このマンションを貸して生活の面倒をみていたのだ。亡くなったのは三年程前かな…』
「…ちっとも知りませんでした…」
『ああ、知っているのは私と秘書の上原と十郎だけだ…葬式も略式だった…病弱なところは小夜子も似ていたな…』
彼と小夜子の母親の間に何があったかは分からないが、きっと大切な人だったのだろう、と友弘は感じた。
『それから十郎は自分一人のくつろげる場所としてここを利用していたようだ。女を囲う訳でもないので私も黙認していたのだが、最近誰かが暮している様子だったのでな…ちょうどお前と連絡がつかなくなった時期と一致するので確かめようと思ったのだ…』
玄雄はふっと息をつぎ、言葉を止めた。友弘は玄雄と話しながら次第に落ち着かなくなってきた。彼はどこまで事情を知っているのだろうか…
『…友弘…一体何があったのだ…?』
「……………」
『十郎はなぜお前をここに連れて来たのだ?それに果月に教えていないのは何故だ?一体お前達の間で何があったのだ…?』
「……………」
玄雄に何を言えばいいのだろう?真実を彼に告げるのか?もし、知ればきっと玄雄は苦しむだろう。誰が悪い訳でも誰のせいでもないのに、苦しむ人がいる…
十郎、果月の顔が脳裏に浮かび上がり、友弘は黙り込んでしまった。
『…友弘……』
「…何も…ありません……」
『…友弘…正直に答えてくれ…』
「本当に何もありませんよ…十郎がどれ程の人物か、お義父さんが一番よくご存知でしょう」
『……………』
「お義父さんが心配なさる必要はありません」
そうだ、玄雄を巻き込んではならない。これは自分がけじめをつけねばならない問題なのだ。果月の為にも、十郎の為にも…
今の俺は二人とも不幸にしている…
自分が動きださねばと、友弘は強く感じた。
『……分かった……』
幻雄は十郎も同じ言葉を自分に言ったのを思い出し、これは自分が介入するべきではないと悟った。
『だが何か助けが必要になった時は言ってくれ。遠慮は無用だ…』
「…はい…あの…お義父さん…」
『なんだ?』
「…お義父さんはこのマンションに入れますか?」
『ああ、鍵は私も持っているが。どうした?』
「…お願いがあるのです…」