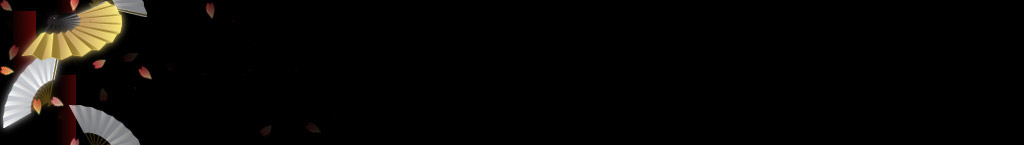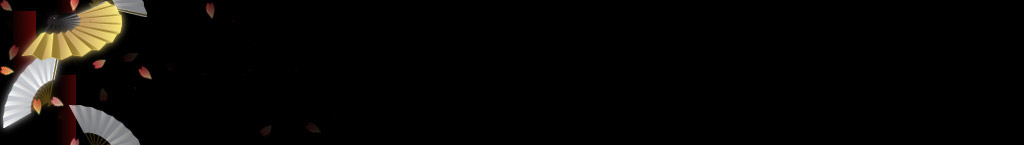
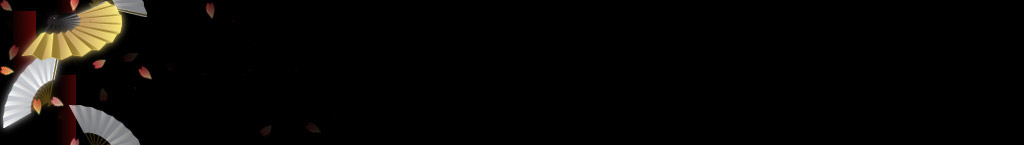
秘すれば…(投稿用)6
六
その日の稽古は一日中十郎が不在だったので、弟子達はいぶかし気であった。出張でもない限り、一度は稽古場に顔を出すのが彼の常だったからである。
「先生、今日はどうしたんだろうな。玄雄先生もここんとこ稽古場にいない時が多いし…果月、お前何か聞いてないか?」
後片付けを始める武の問に、隣にいた果月は首を振る。友弘が消えてから果月は十郎を見張る為、すべての稽古を近江家で受けていた。稽古場にやってくる十郎を廊下で待ち、手をついて教えてくれ、と懇願するのだが彼は無視し続けている。そんな毎日繰り替えされる果月の姿に、弟子達の間ではいろんな噂が飛び交っていた。訳を聞こうにも果月から漂う気迫に詳しく詮索出来る雰囲気ではないのだ。
『何があったんだろう…?あの果月が嫌っている十郎先生に手をつくなんて…』
武も気にはなっているが、果月の無言の拒絶を感じて聞けずにいる。
『でも、二週間もこんな状態が続いているし、果月も相当煮詰まってきてるようでやばいんじゃないのかな…』
最近の果月は殺気を漲らせており、顔つきも悪くなって誰も怖くて近付けない。稽古場で話かけられるのは武と玄雄だけになってしまっている。
『このままじゃ…良くないよな……』
どういう事情があるか聞こうと武が口を開きかけた時、稽古場の戸が開き、そこに十郎が立っていた。部屋にいた皆は彼に向かって急いで頭を下げる。こういった行動は強制されているのではなく、皆が十郎を尊敬しているので自然とそうなったものである。十郎は、腰も折らず自分に鋭い眼差しを向ける男だけを見ていた。黒の着物にグレーの袴を身につけた十郎は堂々とした存在感を漂わせていて、果月は余計に癪に触る。
「来い…」
一言だけ告げると十郎は立ち去ったので、果月は急いで後を追う。
『…なんの用だ?何か話すのか…』
果月の胸は不安と期待で高鳴り始める。屋敷の一番奥にある十郎の私室に行くと、二人は座卓を挟む形で腰を降ろした。果月はいつもの落ち着き払った十郎の顔が、心持ち青ざめているように見えた。その彼が座卓の上に一通の封筒を置き、果月の方へ差し出す。
「お前に手紙だ……」
果月は急いで手に取り、中にある便箋を取り出して広げた。思った通りそれは友弘からの手紙であった。
『果月、元気にしているかい。俺の方は大丈夫だよ。実はもう一度修行し直そうと思って、ある著名な能面師の方のところへ弟子入りを決めた。もっと強くなって、揺るがないお前への想いを持てるようになりたいんだ。いきなりこんな話をしてすまないと思っている。会えないまま旅立つ事を許して欲しい。お前に会うと決心がぐらつきそうで怖いんだ。本当にすまない。お前と暮らした十二年間は夢のように楽しかった。その想い出は俺の心の一番美しいところにある。決して忘れない。離れていてもずっと愛している。では、いつか会えるその時まで…小鳥遊 友弘』
果月は意味が分からなくて、何度もその短い手紙を読み直した。だが、何度読んでも自分が望んでいた言葉は書かれていなかった。戻るも、帰るとも、なにより弟子入り先が書いていない。教えるつもりがないからだ…
いつか会えるその時まで…?
『…なんだ…これは…友弘は何を言っている…つまり…』
これは別れを告げる手紙なのだ…
「…まさか…どうして…」
果月の頭の中は混乱して何を考えたらいいのか分からなくなった。こんな事が起こる訳がない。友弘がいなくなってしまうなど、まったく予想していなかった。会えないのは今だけ、この事態を打開すればきっとすぐに会えるのだと信じてきたのに、その彼が遠くへ行ってしまうなど…
なぜだ……!
果月は全身を震わせながら手紙を食い入るように見つめる。そんな彼の様子を十郎は黙って目に映していたが、心は別のところにあった。十郎は昨夜の出来事を思い出していたのである。
昨夜の深夜、十郎は友弘のいるマンションを訪れていた。友弘から電話があり、弟子入りを決めたからこの土地を離れると言ったので、許さないとはっきり伝えに来たのだ。予想していたのか友弘は驚かず、落ち着いた様子で十郎を出迎えた。
「これを、お義父さんに返しておいてくれるかい…」
友弘が差し出したのは『若女』の本面であった。『若女』は昔、月華流の家元の「我が流派の名物となる女面を打ってくれ」という依頼を受けて、有名な能面師が制作した面である。純粋で美しい『若女』は家元の希望どおり、月華流の看板に相応しい素晴らしい女面となった。この本面を借りるという事は『若女』の『写し』を打ったという意味だ。
「…『若女』を打ったのか……」
「…ああ…初めて打った……」
三日程前、玄雄に頼んで持ってきてもらったのだ。『若女』を打つのはもっと実力をつけてから、と友弘は決めていたが、自分の裡でのけじめをつけようと一心不乱に打ち上げたのである。無心に、ただひたすら無心に打ち上げた。自分を研ぎすます為に、心を強くあらせる為に…
心を真っ白にして考えたかった。自分が十郎と果月の為にしてやれる事を…
「…お前…もう一度修行しに行きたいそうだな…」
「ああ……」
「どこへ行くつもりだ?」
友弘は軽く首を横に振った。
「…告げるつもりはないんだな…」
「ああ……」
「…俺が許すと思っているのか…?」
「……十郎……」
「絶対に行かせない…」
「…十郎…俺は行かなきゃ…」
「駄目だ……」
「…俺は…強くなりたいんだ…」
「なに……?」
「…俺は弱い男だ…もう一度、能面師という仕事と共に自分を見つめ直したい…」
「……………」
「このままじゃ俺はお前に対しても、果月に対しても中途半端だ…」
どちらの想いも大切だけれど、両方の想いに応えるのは不可能だ。分かっているのに、どちらも傷つけたくないと思ってしまう…自分の気持ちは決まっているのに、その想いに飛び込む事に罪悪感を感じる自分がいる。愛して欲しい人に愛された記憶がないから、愛されない辛さを知っているから戸惑ってばかり。だが、そんな曖昧な態度は二人の想いを侮辱しているのと同じだ。
「……駄目だ……」
「……十郎……」
「行かせないぞ」
「…十郎は俺にどうして欲しい…?」
「………………」
「…俺は…何をすればいい…?」
十郎は懐から小柄を取り出し、二人の間に置いた。
「…お前の命が欲しい……」
愛されないのなら彼を誰にも渡したくない。自分も彼に命を捧げ、永遠に自分のものにするのだ。
昨夜、玄雄から話を聞いてすぐにここに駆け付けなかったのは、後始末をする為だった。自分がいなくなってからの混乱を最小限に食い止める手筈を済ませてきたのである。未練も戸惑いもなく、裡に秘めた炎に飛び込む事を想像すると、十郎の身体に甘美な震えがはしった。
「……分かった……」
友弘は動揺もみせず、簡単に答えたので十郎は一瞬耳を疑った。友弘の手が伸び、小柄を掴んで鞘を抜く。十郎は黙ってその姿を見つめていた。
「…お前は…駄目だぞ……」
少し淋しそうに微笑んで言った友弘の声に、十郎は全身がぐにゃりと歪んだような衝撃を感じる。今、自分が見ているものがいきなり現実となって目に飛び込んできた。冷めていた頭に急速に熱が戻ってくる。
『……本気だ……』
彼は本気で自分に命を捧げようとしているのだ。目の前で友弘が死のうとしている…本当に自分は彼の命が欲しいのか…彼を自分のものにするというのは、こういう意味なのか…十郎の心が散り散り乱れ、激しい痛みを胸に感じる。
友弘が深呼吸をして両手で小柄を持ち直す。彼も今日一日であらかたの後始末はすませていた。能面教室には新しい能面師を紹介したし、仕事はちょうど区切りの時で未完成のものはない。自分が遠くへ行くにしろ、何かが起きるにしろ、いなくなるのは確実だったからだ。
瞳を閉じ、友弘は喉に刃を突き立てようと手を出来るだけ遠くに離す。もう会えない果月の姿を思い浮かべて、無意識に微笑みがもれる。最後に深呼吸をして覚悟を決めた友弘は、刺そうと喉元に刃を向けた。
だが、刃が喉を貫く寸前、十郎の腕が友弘の手を止めた。渾身の一刀だったので、止められても友弘はすぐに力を抜けなかった。十郎は慎重に小柄を友弘の手から奪い、遠くへ放り投げる。小柄は壁にあたって畳へ落ちた。身体の緊迫が解けた友弘は畳に手をついて、がっくりと項垂れる。二人は止めていた息を吐き出し、荒い呼吸を繰り返した。
「……どうして……」
十郎が苦しそうに声を出す。
「…どうして…そんな簡単に俺の言う通りにするんだ…!」
友弘の肩を掴んで十郎は激しく揺さぶった。
「どうして抵抗しない!どうして俺を罵らない!」
「…十郎…俺がお前にしてやれるのはこんな事ぐらいしかないからだ…」
「……友弘……」
「…お前にどんな辛い思いをさせてきたか分かっているつもりだ…お前は俺にとって大事な人なのに…」
「…どうして…そんな風に思えるんだ…」
自分が彼にした事を考えると、十郎は友弘の言葉が信じられなかった。
「…小さい頃、俺が孤児だっていうので虐められたらいつも庇ってくれたろ…」
「…その程度の事で……」
「俺はお前の友人なのが誇らしかったよ…お前はいつも大勢の人に囲まれて頼りにされていたな…」
「…それは俺が跡取りだからだ…」
「…でもお前はそれにふさわしい人だよ…」
「……………」
「不思議だったんだ…俺と十郎とじゃ家柄も環境も性格も違うのに、俺は誰よりも十郎を身近に感じてた…俺の気持ちを誰よりも理解してくれているって…それがどれだけ俺のやすらぎとなったか分からない…だから、十郎…お前は大事な人なんだ…」
それは俺も同じだった、と十郎は心の中で呟いた。
「…ある日気がついたんだ…十郎と俺は同じだって…心の底で孤独を抱えているんだって…」
「……友弘……」
頂点に立つ者は孤独である。どれだけ大勢に囲まれようとも、どれだけ賛辞を送られようが決して癒されぬ孤独。家長となる十郎は一生その孤独の中で生きねばならないのだ。十郎にとって更に不幸だったのは、彼にはそれに堪える度量も、才能も備わっていた事である。友弘だけが拠り所だった。あの頃はお互い大切な友人で、同じ想いを抱えていたのに、いつから違い始めていたのだろう…
「…だから…少しでもお前の力になりたかった…お前が俺にやすらぎを与えてくれたみたいに…」
「……………」
「…なのに俺は…お前を苦しめてばかりだった…」
「お前が…俺を…?逆だろ…」
「…十郎…お前をいつも追いつめていたのは俺だった…」
彼が爆発するのはいつも自分に対してだけだ。六年前の時も、このマンションに連れて来た時も、原因はいつも自分だったと友弘は知っている。
「そして一番お前を苦しめる人を…想ってしまった…」
十郎は自分を見つめる友弘の澄んだ瞳を覗き込んだ。その奥にある光を…淋し気で、すべて悟っている美しい瞳…一番お前を苦しめる人、と言った彼の言葉に十郎は戦慄を覚える。
「…お前…知っているのか…あいつの父親が誰だか…」
友弘は何も言わなかったが、沈黙は答えだった。
「…知っていて…知っていてどうして小夜子と結婚した?どうしてあいつの父親になったんだ!」
「…お前の子供なら果月は優しくていい子だと分かっていたからだ…」
十郎は苦しくなって双眸を閉じた。彼の残酷な優しさが身体中に突き刺さるようだ。
21年前、小夜子は失踪する前夜に十郎の部屋に来たのである。そして、愛を告白した。だから結婚する前に一度情けをかけて欲しいと言われて十郎は驚愕した。
どうして小夜子を抱いたのか自分でも分からない。まだ友弘への想いは自覚しておらず、ただ小夜子の縁談に落胆している彼を見て苛立たしく思っていた。頭の中で友弘の事や小夜子の言葉と涙がぐるぐる回り、混乱していた。
彼女を哀れに思ったから抱いたのか…家に対する反抗からなのか…理由はそのすべてであり、どれでもないような気がする。もしかしたら友弘の代わりにしたのかもしれない。小夜子を抱いている時、十郎は友弘の事ばかり考えていて、その時自分の想いが恋だと初めて気付いたのだから。
後悔した十郎は彼女が失踪した時ほっとした。もう、このまま戻ってくるなと願いさえした。しかし、彼女は帰ってきた…あの夜の子を宿して…
「……いつ…知った……?」
「…俺との結婚話が持ち上がった時、小夜子さんが話してくれた。だから結婚なんかしなくていいって…でも俺は彼女がいなくなった後、自分と同じ孤独を果月に感じて欲しくなかった…」
きっと優しくていい子だから…十郎と小夜子の子供だから…自分が早川に愛されなかった時と同じ痛みを感じて欲しくなかった。
『ごめんね、ごめんね友ちゃん…私、十郎が好きなの…ずっとずっと好きだったの…』
彼女は何度も何度も謝った。小夜子は一度きりの十郎との逢瀬を胸に死ぬつもりだったらしい。だが、熊野の森の奥にある寺の住職に見つかり、止められてしまったそうである。しばらく寺に御厄介になり、このままここにいようかと考え始めていた矢先、懐妊に気付いた。
『私、嬉しかった…これで、結婚せずにすむ。十郎の側にいられるって…きっと神様が味方してくれたんだと思った…でも駄目ね…十郎は決して私を許さないわ…それでも…彼の側にいたかったの…』
小夜子が私生児を産み、家名に泥を塗った女として蔑まれながらも近江家にいたのは、一途に十郎の側にいたいからだった。しかし、自分の寿命があまりないと悟った時、果月の行く末が心配になったのである。本来なら十郎は私生児というぐらいで、甥に冷たい態度をとる人間ではないが、自分に対するの憎しみを代わりにぶつけられるのではないかと恐れたのだ。家名を重んじる親戚筋の者は追い出そうとするかもしれない。その時の小夜子はわが子を愛する母親だった。友弘は母親の顔をしている小夜子に、知らない自分の母の姿が重なって見えた。果月には早川に引き取られた自分の姿が…
『俺が果月の父親になるよ…父親としてあの子を愛して大切に育てるよ…』
そう約束したのに……
「…俺は父親になれなかった…十郎…お前も苦しめた…」
「…友弘…俺は…お前を利用したんだな…」
「……十郎……?」
「自分の罪を消す為に……」
十郎は小夜子と果月の存在を徹底的に無視した。いない者達と思い込む事で、自分の罪から目を逸らしたのである。友弘が小夜子と結婚した時は衝撃だった。一瞬、小夜子が自分に気持ちに気付いて復讐したのかと疑いもした。だが、心のどこかで果月に父親ができる、と安堵している自分がいた。これで果月に私生児という負い目はなくなる。小夜子も未婚の母ではなくなるのだから、自分が罪の意識をもつ必要はもうないのだと。
「…卑怯な…男だ…」
利用したのは小夜子でなく自分だ。本当に結婚を止めたければ、事実を言えば良かったのだ。果月の父親は自分だと……
言わなかったのは罪の意識から逃れたかったからで、なにより、友弘に軽蔑されるのが怖かった。彼に対して誠実であるより、自分の矜持を選んだのだ。
「…罰だと思ったよ…」
自分の罪の証である果月が友弘を愛したのも、彼の心を手に入れたのも…罰なのかと…だから、認めたくなかった。
「…十郎…お前は優しくて強い人だよ…」
「俺が…優しい……?」
「本当に冷たい人間ならどんな手段を使っても、小夜子さんと果月を追い出しただろう…でも、お前はそれをしなかった…蔑みもしなかった…責任を彼女だけに押し付けたりもしなかった…」
誤魔化しもせず、自分の過ちを受けとめていた。だからいつも苦しんでいたと友弘は知っている。それなのに、彼の苦しみに気付いておきながら、果月を想ってしまった。
「……友弘……」
「俺は…お前を憎んだ事はない…罰を与えようなんて思った事も…苦しめるつもりもなかった…でも…すまない…俺は…」
「……友弘……」
「…俺は…愛してるんだ…彼でなければ…駄目なんだ…」
自分の心は彼のものなのだ…
「…だから…お前に俺が出来る事があるなら…したいんだ…」
命が欲しいのなら、あげても良い…友弘の瞳が十郎にそう訴えかけてくる。
「どうして…あいつなんだ…」
十郎の問いに友弘は少し顔を伏せる。
「…果月は…俺のずっと欲しかったものをくれた…」
小さな果月が自分の所にやって来たあの夜、果月はなんの躊躇もなしに自分がずっと求めていたものを与えてくれたのだ。自分の名を呼び、抱き締めてくれた。そしていつの間にか彼を一人の男として…
「…幸せになって欲しいと願ってる…そして、十郎…お前も幸せになって欲しいんだ…」
「…許して…くれていたんだな…」
友弘の頬にそっと手を触れ、もう一度彼の美しい瞳を覗き込む。
『もういい……』
もう、十分だと十郎は思った。十郎はゆっくりと友弘の身体を抱き締める。腕の中に収まってしまう、小さな身体をした彼…本当に欲しかったのは彼の心だ…それだけしか欲しくなかった…けれど…駄目なのだ…
『お前の心は、あいつのものなんだな…』
十郎は抱き締める手に友弘の体温を感じていた。無理矢理肌を合わせた時よりも、今、彼を抱き締めているこの時に、彼のぬくもりを痛い程感じる。たとえ愛されなくても、彼は命を捧げる程自分を大切に想ってくれているのだ。何より、友弘は自らここを出て行くと自分に告げた。玄雄と連絡がついたなら、勝手に出て行く事も可能だった筈なのに、自分の気持ちを大切にしてくれたのだ…何も与えてやれなかったのに…それだけで、もういい…
「…友弘…お前に…愛されたかったよ…」
「……十郎……」
友弘は十郎の腕の中で、彼の声にならない叫びを聞いた。
十郎の抱擁はいつしか息も出来ぬ程強いものとなっていたが、友弘は黙って彼の無言の叫びを受けとめた。
「…お前が…何かしたのか…」
果月の震える声に、意識を今に戻した十郎は視線を向ける。
「十郎…お前…友弘に何か言ったのか…だからいきなり弟子入りするなんて言ってるのか…!」
十郎は無言で文机の下から木箱を取り出した。
「…友弘の打った面だ…」
果月は奪い取るように箱を掴み、蓋を開けた。中には美しい『若女』の面があった。果月は手にとってそれを見つめる。清楚で愛らしく、深みのある表情をした面で、今迄見たどの面よりも純白な美しさがあった。まさに月華流の名物である面にふさわしい美しさだ。清々しい香りが果月を包み、友弘の作に間違いないと確信する。
『『若女』はもっと自分の力がついてから打つと言っていた筈。それなのに、何故今?』
訳のわからない胸の悪さを覚え、果月の頭に心臓の音が耳鳴りとなって響いてくる。
「もっと素晴らしい『若女』の面を打てるようになりたいそうだ…」
「…十郎…お前が決めたのか…」
「……………」
「そうなんだな!お前の差し金だな!どこに行かせるつもりなんだ!答えろ!」
混乱した果月は目の前にいる憎い男に憤りのすべてをぶつけようとしていた。怒りを全身を漲らせ、十郎の襟首を掴もうとするが、その手は十郎に払われ、替わりに左頬に彼の拳を思いきりくらう。すごい勢いで果月の身体は後ろに飛んだ。目の前に星が散り、血の味が口腔内に広がる。ふらつく頭を振って起き上がろうとしたが、十郎が襟首を掴んで締め上げてきた。
「……ぐ……」
強い力で絞められ、果月は息が苦しくなる。半ば倒れた体勢なので身体が満足に動かせず、ふりほどけない。
「……貴様に分かるか……」
十郎の押し殺した声が聞こえる。
「…俺はずっと友弘を見てきた…貴様が産まれる前からずっとな…」
「……な…何……」
「決して成就できない想いだと分かっていても、諦められなかった…ずっと想い続けてきた…だが、あいつが選んだのは俺じゃない…」
自分ではなかった……
「…その俺の気持ちが貴様に分かるか…!」
十郎は掴んでいる襟首を引き寄せて、果月に顔を突き付ける。十郎の裡から吹き上げた炎が全身を包んでいるようだった。これ程までの情熱を秘めていたのだ。彼の感情の爆発を肌にピリピリ感じて、圧倒された果月は言葉を失う。十郎は突き放すように果月の身体を離して背を向ける。その背中からも立ち上る蒼い炎が見えた。
「…貴様が憎い…心底な……」
「……………」
「あいつの心を手に入れている貴様がな…!」
こいつはいくら振払ってもついてくる自分の影。自分の過去の過ちが形となった忌々しい存在。日ごと自分に似てくる果月が十郎は認めたくない存在だった。いつか呑まれそうで…しかし、この果月だけが、友弘の求めていたものを与えたのだ。自分の矜持も情熱も友弘の為ならすべて差し出すだろうこの男だけが。自分では与えてやれなかった…
十郎の激情を感じながら、果月の身体は徐々に冷たくなっていった。絶望を感じて血の気が引いていく。友弘が行ってしまうという事実が、確信として心に迫ってきたからである。
行ってしまう…友弘は行ってしまう…この十郎も彼に置いていかれる人間なのだ…!
果月は畳の上に転がった美しい面を拾いあげる。
いやだ…堪えられない…友弘が遠くへ行ってしまうなど…あの日、自分の腕の中で眠る彼の寝顔を見たのが最後になるかもしれないなんて。
「…今…友弘はどこに……」
かすれていたが果月はなんとか声をしぼりだした。
「………………」
「どこにいるんだ……!」
このまま会えないのか?会えないまま行ってしまうのか?絶対に嫌だ!
「頼む、教えてくれ十郎」
果月は起き上がり畳に手をついた。恐ろしくて全身が震え、感情の昂りから瞳が潤んでくる。
「……愛してるんだ……」
言葉なんかでは言い表せないほど…
「………………」
知っている…十郎は心の中で応えた。友弘に愛された男だという事も…
十郎は懐から小さな紙を取り出し、果月の傍らに膝をついて目の前に置いた。
「ここに書いている場所にいる…明日の早朝発つ…」
果月は紙切れを掴んで立ち上がる。
「だが、引き止めるな…」
十郎の言葉に一瞬彼を見つめる。しかし、果月は彼の言うとおりにするつもりなどなく、面を持ったまま部屋を飛び出そうとした。
「あいつに縋るな!」
背中に放たれた十郎の声に、果月の足が止まる。
「…友弘は…人を簡単に許してしまう…俺はそんな彼の優しさに甘え、利用した…俺に彼を想う資格はない…」
「………………」
「だが友弘は俺の気持ちを無視したまま、お前の元に留まるのを自分に許さなかった。俺がどう言おうと決心を変えなかった…強くなりたいと言ってここを離れると決めた…」
「………………」
「お前が止めたとしても同じだ。友弘を苦しめるだけだ…」
果月と同じく十郎も友弘の行き先を知らない。このまま会えないかもしれないと考えると苦しかったが、それでも彼のだした結論なら受け入れてやろうと思った。資格のない最低の男だったとしても、友弘を愛する事だけは誰にも負けたくなかったからだ。友弘の言葉も想いも、出した結論も行動も、黙って受け入れよう…俺という重荷から解放してやろう…そう十郎は決意したのである。
「…いつか帰ってくる…彼を…信じて…行かせてやれ…」
果月は全身を小刻みに震わせて聞いていたが、堪えられなくなって部屋を飛び出す。稽古場を抜け、近江の家を走りでるが、果月の足は止まらなかった。行き先など考えてもいない。ただじっとなどしていられなかった。裡から突き上げてくる熱い想いを持て余してひたすら走る。
『あいつに縋るな』
十郎の痛い言葉が頭に響く。
俺は友弘に縋って引き止めようとしている。それが彼を苦しめるのか?でも、堪えられないんだ!
友弘が自分の前からいなくなってしまって、その後自分はどうすればいい?一人で残される自分を想像すると怖くてたまらない。母を失った時の孤独を思い出して果月は身震いした。友弘がいたから堪えられた。自分が一人ではないと感じていたから、いつも彼が側にいて微笑んでいてくれたから…彼がいてくれればそれだけで良かったのに!その友弘が去っていく?自分を置いていってしまう…どうしてだ、どうして俺を置いていってしまうんだ!あんな簡単な手紙だけを残して…
――いつか会えるその時まで――
いつなんだ…いつ会えるというんだ…一年後か、二年後か、五年?十年?いやもっとなのか…!
『俺はどうすればいい……?』
この身も焦がすような想いを一体どこにぶつければいいのだ。自分自身をも焼き付くす程のこの想いを。
外はすでに日が暮れていて、辺りは暗闇に包まれ始める。果月の心も暗い闇に覆われ、あてもなく彷徨い続けていた。
早朝、友弘は身支度を整え、マンションを出た。外には呼んでいたタクシーが止まっている。乗り込む前に友弘は辺りを見渡し、朝の清々しい空気を吸い込んだ。マンションの外観も、辺りの景色を眺めるのもこれが初めてである。今まではバルコニーの狭い範囲内から見るだけだったから、辺りがこんなに殺風景だと思わなかった。マンションの側に川が流れ、土手沿いに遊歩道があり、犬と散歩している人が一人いる。少し離れた所に小高い丘があって、公園でもあるような雰囲気だが他には何も無い。日が高くなればたくさんの人が行き交うかもしれないが、今は休日の早朝なので人気はほとんどなかった。友弘は深呼吸をしてタクシーに乗り込んだ。出来るだけ何も考えないように努めて、空港に行くように指示する。車が動きだして友弘はふっと丘の方へ目を向けた。途端に、息が止まる。
そこに、果月がいた……
練習着の袴姿で、うちひしがれて立っている…
淡い朝日の中、まだ白い空の下、遠く小さな影だったが間違うことなく彼だった。顔が見えなくても自分が打った面をかけているのが分かる。哀しみを現わすクモリの表情をして、彼を包む空気さえも泣いていた…
せり上がってくる苦しさを覚えて、友弘は口元に手をあてた。指の間から微かに嗚咽が洩れる。
「どうかしましたか、お客さん?」
「…いえ、なんでもありません…」
靴紐を結ぶ振りをして前屈みになり、運転手の視線から逃れた。
『どうして離れなければならないんだろう…こんなに、想っているのに…』
何度も同じ考えを頭の中で繰り返す。涙が足元にぽたぽたと落ち、車を飛び出して果月の元に駆け付けたい衝動を必死に押さえ込む。
『でも駄目だ…このままじゃ俺は二人を苦しめるだけの存在だ…』
十郎の想い、玄雄や千賀子の存在…それらを無視して自分だけ果月の元にとどまるなど友弘にはできなかった。果月を愛した事によって苦しむ人がいるのに自分は堪えられない。今の自分のままでは、いつか果月を愛した事を後悔する日さえくるかもしれない…全てをぶつけて愛してくれた二人に対して、自分はあまりに弱い…
友弘はもっと強くなりたかった。二人の想いを受け止められるぐらい…自分の想いを貫き通せる程の強さを持ちたい。そして自分の愛している人は果月なのだと、誰にも恥じる事なく言える人間になりたい。それが十郎の想いに、誠実であれる事なのだ。
能面師という誇りに思っている仕事と共に自分をもう一度見つめたい。大切なものが何なのか、一番望んでいるものを掴みとる力を手に入れる為に。
強くなって、いつかきっと帰って来る。その時、果月が自分を愛していなくても、彼を想い続けていられるだろう。決して後悔しないだろう。
『果月…俺は待っていてくれとは言わない…憎んでも、恨んでもいい…でも俺はお前を愛しているよ…』
ずっと…いつまでも…
友弘は涙を拭くと、顔を上げて前を見据えた。もう、果月の姿は視界から消えたが、瞼の裏には彼の姿が焼き付いていた。いつまでも忘れない光景として…