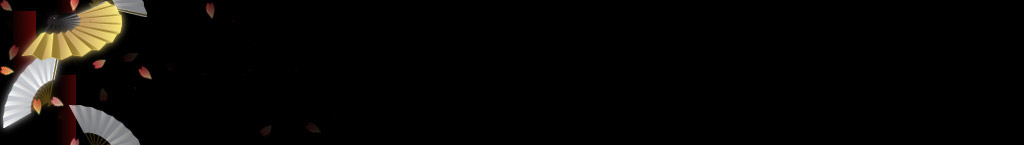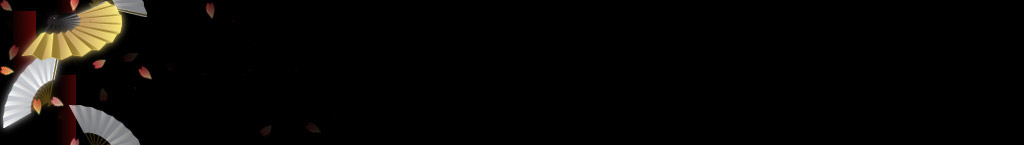
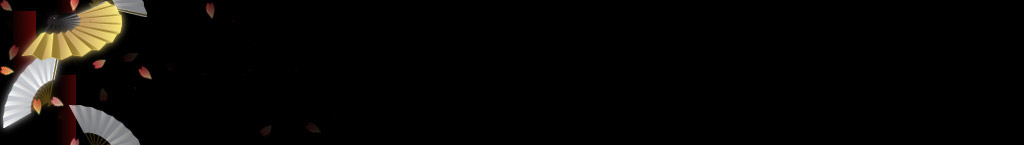
秘すれば…(投稿用)7
七
――三年後――
長月の某日、秋の演能会が朱雀能楽堂で行われた。近江十郎の出演する演目のチケットは、いつもあっという間に完売するが、特に今回は三年振りに小鳥遊果月が共演するとあって話題をよんでいた。二人が舞う演目は『恋重荷』で、十郎がシテの山科荘司(菊守の老人)果月がツレの女御を演じる。
「果月、十郎先生が呼んでるぜ」
鏡の間で控えていた果月に武が声をかける。果月は装束を着ていたが、面はまだかけていなかった。
「そうか、ありがとう」
「お前大丈夫か?」
「何が?」
三年振りの十郎との共演だ。前回は彼の実力に圧倒され落ち込んでいたが、今回は大丈夫だろうか、と武は少し心配していたのである。が、もうすぐ本番が始まるというのにあがっている様子もなく、むしろ清々しい表情をしている果月を見て、武は今日の舞台の成功を確信した。
「なんでもない。今日の舞台、頑張れよ」
「ありがとう」
すぐさま果月は十郎のいる控室に向う。
「果月はどこだ?さっきまでここにいた筈だが」
ちょうど入れ違いに父親の須藤がやって来る。
「ああ、十郎先生に呼ばれて控室の方に行ったよ。なんかアドバイスでももらうんじゃない?」
「そうか……」
「あの二人の関係も変わったね。三年ぐらい前までは険悪ムードだったのに、今じゃ子弟関係だもんな」
「本当に良かったよ。玄雄先生は高齢だし、ずっと果月に教えている訳にもいかないから」
「変わったって思い始めたの、一年ぐらい前かな。ちょうど十郎先生のお嬢さんが誕生した頃」
「やはり親になると違うだろう。子を愛する気持ちが分かると」
「へ〜そういうもんか〜」
いつ頃からだろう、武は果月が急に大人になっていくのを感じていた。『舞』がどんどん研ぎすまされたものとなり、同時に性格も穏やかになっていった。それまで口数は少ないが、感情の起伏は激しい方だった。今は柔らかく人を包みこむような空気を纏うようになったのである。懐が大きくなったと感じる。
『あの柔らかさは小鳥遊さんを思い出すな…』
「そういや、小鳥遊さん今日も来ないね。せっかく果月の舞台なのに」
「修行中の身だと自由がきかないんだろ」
「でも一度も帰ってきてないんだろ。果月の方は養子の話も断ってあの家にいるのに」
「あれは十郎先生が断ったみたいだぞ。もちろん果月の意志もあるが」
「え、そうなの?」
「ああ、果月を養子にだせば小鳥遊さんが一人になってしまうだろ。あの人は他に身寄りもないし、可哀想だって言ってな」
果月が養子の話をきっぱり断ったのは、友弘と親子でもいい、繋がりを残しておきたかったのである。十郎もそれさえもなくなってしまうと友弘が辛いと考え、玄雄や周りを説得して話を白紙にした。
「そうだったのか〜」
「さ、武。お前も今日の舞台はしっかり見ておけよ」
「言われなくても分かってるって。果月の晴れの舞台だもんな」
どんどん先を行く友人の姿に、俺もしっかりしなくては、と気をひきしめる武であった。
「果月です。失礼いたします」
部屋の前で果月が膝を折って声をかける。入れ、と返事がしたので障子を開けて中に入ると、装束を身につけた十郎が待っていた。果月は装束が皺にならぬよう気をつけながら向いに腰を降ろし、頭をさげて挨拶する。
「お呼びとお伺いしましたが」
「…今日の面はこれを使うがいい…」
十郎は蓋の開いた木箱を差し出した。中には『若女』の面が納めてあり、あの時の友弘の面だと果月は一目で分かった。見るのが辛くて、倉庫の奥に自らしまい込んだものである。
「…彼の面は縁起がいい…」
信じられぬ思いから果月は十郎の顔を凝視した。『若女』は家元か長老クラスの師範の許可がなければ使用を許されない面である。
「『若女』は月華流を代表する面だ。心してかけろ」
「……肝に命じます……」
「…お前はいつか「愛する人の為なら千本の刀を打ってみせる」と言ったな…」
「……はい……」
「では、打ってみせろ。今日の舞台を一本目とし、千本の刀を見事打ちあげればお前を認めてやろう…」
果月は十郎の言葉に目を見開いた。
お前を認めてやろう…
それは、友弘と共にあるのを認めてくれるという意味か…
「どうした?自信がないのか?」
果月は手をついて深々と頭を下げる。
「…ありがたく…お受けいたします…」
胸が熱い想いで溢れ、苦しくなるが決して不快ではなかった。果月は顔を上げて、自分の前に座る最高の能楽師の姿をじっと見つめた。
果月はこの男を憎んでいるが、同じくらい尊敬の念も抱いていた。友弘が去ってからも、果月はすべての稽古を近江家で受けた。友弘から何か連絡があった時、十郎に握り潰されないように見張る為、という名目だったが、今考えると、同じ苦しみをもつ彼の側にいたかったのかもしれない。憎かったが、自分の味わっている苦しみを知っているのは彼だけだったからだ。またも果月は十郎への憎しみで自分を支えようとした。そして十郎の舞を見れば見る程、彼の凄さを知っていった。
感情を蓄積し、心を解き放つ……
十郎は激しい情熱も、苦しみも、哀しみも胸の奥深くに秘め、美しい華として舞台に散らせていく。その美しさ。緊迫感の中で放たれる無の香りに人々は酔いしれるのだ。
彼の心を真に実感したのは先日行われた『恋重荷』の申合の時である。
『恋重荷』の演目は、身分不相応にも宮中の女御に恋した老人の哀れな話だ。老人の恋心を知った女御と家来は、老人には到底持ち上げられない重い荷物を差しだし、持ち上げれば女御と会わせてやろう、と言うのである。老人は必死に持ち上げようとするが持ち上がらない。からかわれたと知った老人は憤死し、死霊となって女御の前に現れる。が、女御の心を悟り、護り神となる約束をして消えていくのである。
必死に重い荷物を持ち上げようとする場面は、老人のせつなさが舞台の空間すべてに伝わり、申合に参加した皆は胸をつまらせた。
『名も理や恋の重荷 げに持ちかぬる この身かな それ及び難き八高き山 思ひの深きわたつみ如く 何れ以つてたやすからんや(その名のとおり恋の重荷 持ち上げられない また自分の思いにも堪えられない 女御は高い山の頂上のように手に届かない存在 私の思いは海のように深い どちらが勝るだろうか)』
これ程女御を愛しているのに、最後には彼女を見守り続けていく決意をした老人の包み込むような暖かさ…それは、十郎の想いそのものだった。
果月は十郎がまだ友弘を愛している事。そして友弘が誰を選ぼうとも見守っていくと決意したのを感じた。彼の心の深さに果月は胸が震えた。同時になんと自分は狭小な男なのかと恥ずかしくなった。
舞う十郎の深い想いに圧倒される。同じ『狂い』を舞う彼の想いが伝わり、果月は涙を流さず泣いた。そして、この男を尊敬せずにはいられなかった。今だに『井筒』を舞うのは彼だけである。彼に匹敵する『井筒』は、後百年たたなければでない、とまで言われている。
『一生追いつけないかもしれない…』
彼のいる地点に到達しても、その時十郎はさらに高みに登っているであろうから。まるで偉大な父親のように、いつまでも理想であり続ける男だった。果月はそんな風に感じる。
「まがいものが一本でもあれば承知せんぞ…」
「……はい……」
男としても適わないかもしれない、と果月は思った。他の男に友弘を認めるチャンスを与えるなど自分には絶対無理だから…
「もう行け。心を濁すな…」
「…はい…失礼いたします…」
果月が去った後、玄雄が部屋に入って来る。
「今いたのは果月か?」
「はい」
「何か話したのか?」
「今日の舞台への心構えを確かめておりました」
「……例の話ではないのか?」
「果月を私の養子にする話ですか?あれは私は承諾しておりませんよ」
「しかし、お前は今のところ娘しか誕生しておらんし、跡継ぎが…」
「まだ娘しか出来ないと決まった訳ではありません。仮に娘だけとしても婿をとるという方法もありますし、弟子達の中から近江家の能楽師として相応しい者に継がせるという手もありますよ」
「……しかし……な……」
「お父さん、才能に血は関係ないと言ったあなたが一番血に捕われているのではないですか?」
「何?」
「果月があなたが愛した人の血を受けついでいるから…」
小夜子の母親の血を…
「………………」
「あれは翼を持っています…いつか大きく羽ばたく時がくる…」
そうだ、いつか果月は雄々しい翼を広げて飛ぶだろう…友弘と…もちろん、そう簡単に許すつもりはない。確実に果月が友弘を包める器があるかどうか確かめてからだ。しかし、十郎はその日は必ずくると寂寥感をともないながらも確信していた。
「……十郎……」
「果月は獅子になれぬ男です…」
「分かった…もうこの話はやめよう…」
「……ええ……」
鍛治師の弟子が鬼になって刀を打つ昔話には続きがあった。絶命した弟子を丁寧に葬った後、鍛冶師の娘は弟子の後を追って自害するのである。娘と弟子は愛しあっていたのだ。だが、娘を渡したくなかった父親は難題を言い付け、阻もうとしたのである。結果、弟子を死に追いやり、ついに娘までも失ってしまう。
鍛治師は間違っていたのだ。自分は決して間違えまい…十郎はそっと心の中で呟いた…
まだ友弘を愛しているが、自分の心が決まった今、乱れはない。彼への想いは昇華し、自分の持つ一番美しい華となって心の奥底に咲き誇っている。醜い欲望に変わる事はもうなかった。一年前娘が産まれ、その小さな身体を抱いた時、限り無く愛しい存在を得た時、十郎の心は確実に定まったのである。自分は愛する人でなく、愛してくれる人、必要としてくれる人を選んだのだと。そして自分が幸せなのに気付いた。押し付けられた義務でなく、我が子を、流派を守る道を自分の意志で選んだのだ。
「では私も参ります」
「うむ」
十郎は立ち上がり、息子と共に舞う為に舞台へ向った。
「お、果月急げ、囃子方さんは揃っているぞ」
武の言うとおり、鏡の間にはもう囃子方が全員揃っていて、「お調べ」をするところであった。「お調べ」は開演の合図となる。果月は会釈をして挨拶すると、鏡の前に座った。
「十郎先生なんだって?」
「…面を下さった…」
「そうか良かったな。じゃあな、頑張れよ」
「ああ……」
「お調べ」が済んで、囃子方と地謡が舞台へ出ていく。面をかけた十郎がいつの間にか隣に座っている。二人は一言も話さず、精神を集中しだした。果月が深呼吸を繰り返して友弘の面をかけると、数々の思い出が脳裏を横切っていく。
友弘が去った朝、会わなかったのは自分が彼にしてやれるのはこれしかないと思ったからだ。いつも欲しているばかりだった自分が出来る唯一の事。しかし苦しみが消えた訳ではなく、彼を憎み、恨んだりもした。彼を愛さなければ生まれなかっただろう数々の感情が、重荷となって果月を苦しめた。だが、今も愛している。それは言葉にできぬ想いである。だから果月は舞うのだ。そのすべてを胸に秘めて…
果月は出番に備え、揚幕の前に移動した。囃子方、地謡の気合いが入った音が聞こえ、果月の気持ちが高揚していく。『恋重荷』の女御はある程度の熟練者が演じる大役である。そんな難曲を今から演じる果月だが、武の思った通り落ち着いていた。気持ちのいい秋日和、外では風が揺らぎ、高い空が天にあるのをここでも感じる。適度の緊張感の中、心が澄んでいく…
『俺に、できるだろうか…』
千本の刀を打ち上げる事が…いや、打ち上げてみせる…そして彼をもっとも愛する男に認めてもらうのだ。
果月は二人で暮した家で今もずっと友弘を待っている。彼が微笑みながら玄関から入ってくるのを。彼の作業場が再び清涼な檜の香りで満たされるのを。慌てる必要もなく、ただ彼を信じて待てばいいのだ。友弘も自分と同じように、いつまでも自分を愛している筈だから。恋の重荷は、果月にとってもう重荷ではなくなっていた。美しい想いとして、この胸に抱くもの…抱き続ける強さを自分は持ってみせる…
揚幕が上がり、果月は橋掛かりへ足を運んだ。そこは鬼も幽霊も神さえも存在する空間。見えぬ華が咲きほこり、その香りが満ちる幽玄の世界を果月は舞い上がる。
秘めた心を解き放ち……終
H21.1.15
BLオリジナル小説「秘すれば…」の投稿用に書き直した分をアップしました。
「大丈夫かな〜?」と思っていたのですが、大分時間がたってますし、賞をとった訳でも本に載った訳でもないし;まあ、大丈夫でしょう;
投稿結果はBLトップからリンクしてます。
これから投稿を考えてらっしゃる方の、何かの参考になりましたら幸いです(なるのか?;)
別に賞をとりたかった訳ではなく、プロの寸評を聞きたかっただけですので、私個人としては願いがかなって満足しました。
それに、寸評をもらえなくとも「投稿する」という作業をする事は、かなり貴重な経験になりました。
推敲前は、比べてみれば一目瞭然なのですが、本当に余分なところが多いです;
「客観的に自分の作品をみる」というは簡単なようで難しいのですよね〜痛感致しました;